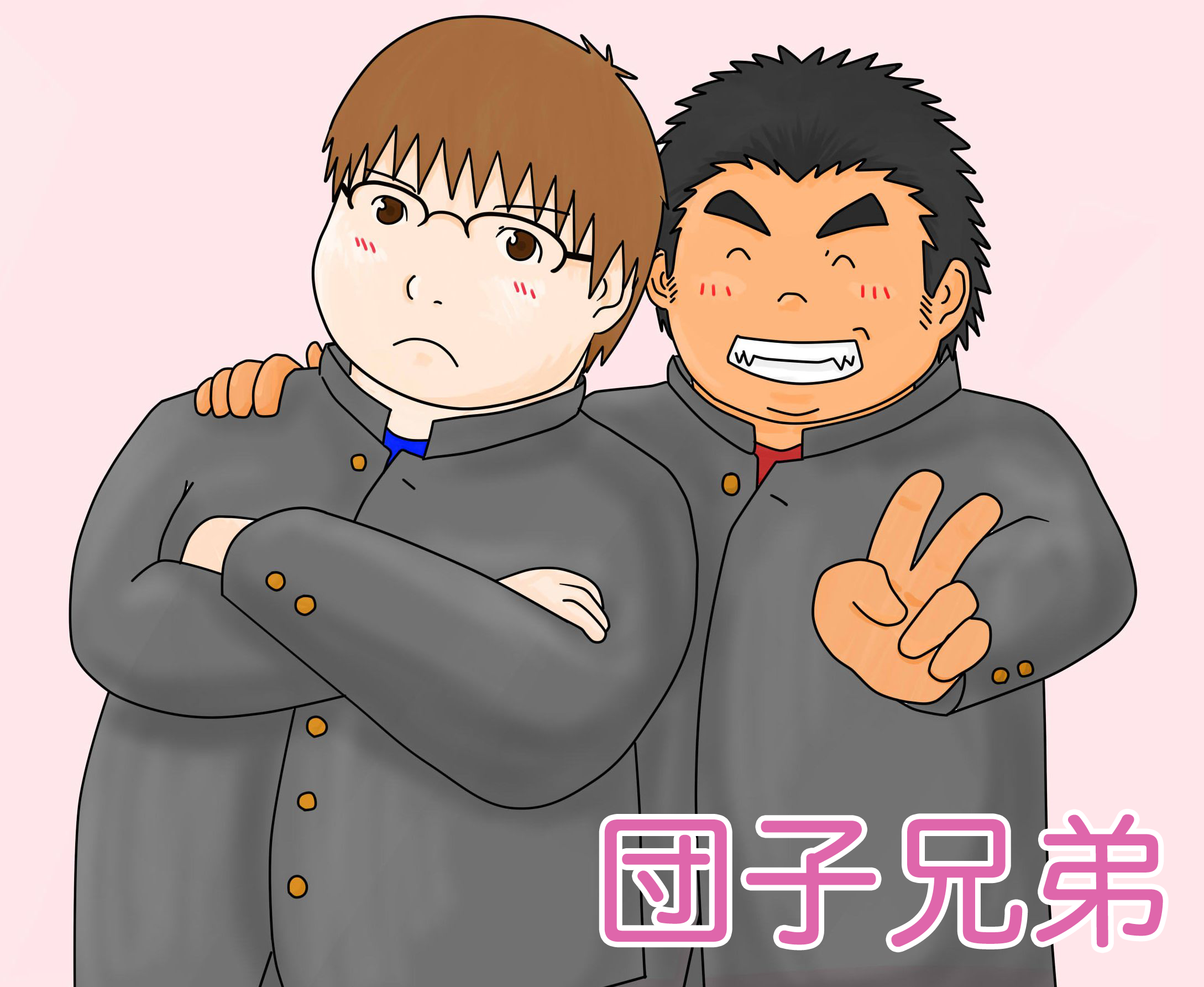一路の夏
小さな頃からぼくは注目されるのが大好きで、いつも人の気を引こうと必死だった
ただ、誰かに構って欲しかっただけだったと思う。実際、性格は内向的で、人見知りは山ほどした。
近所の友達はみんな大人しい子が揃っていて、ぼくは彼らを盛り上げ役を務めていた。夏は川の中に服のまま飛び込んで馬鹿をして彼らを笑わせたりと、やりたい放題の日常を送っていた。
そんなぼくには従兄弟のお兄ちゃんがいて、夏休みになると毎年、お兄さんの家に遊びに行った。お兄ちゃんは大分年が離れているけれど、ぼくのことをすごく可愛がってくれた。
「一路はドラ◯もんみたいで可愛いな〜」
お兄ちゃんはそう言いながらぼくを膝の上に乗せて頭を撫でてくれた。ぼくも甘えるのが大好きだったので、お兄ちゃんの膝の上で調子のいい事をいいながら、お兄ちゃんを笑わせていた。お兄ちゃんの膝の上で寝てしまう事だって何度かあったくらいだ。
そんなお兄ちゃんが笑ってくれるのが大好きだったぼくは、お兄ちゃんが笑ってくれるなら何でもした。テレビのしんちゃんのようにケツだけ星人をやったり、ちんちんにゾウサンを描いて踊ったりもした。大抵パンツを脱ぐとお兄ちゃんは喜んで褒美にお菓子をくれるので、お兄ちゃんの前ではパンツを脱ぐのは当たり前になっていたんだと思う。
暇になるとぼくはいつも裸でおちんちんを突き出してみせた。もちろん、お兄ちゃんのお母さんに見つかると、ぼくのお母さんに報告されて痛い目にあった。
そして、そんなある年の夏の日ことだった。ぼくが小学三年生になる頃のこと。
お兄ちゃんと二人でお兄ちゃんの家でゲームをしていると、珍しくお兄ちゃんの友達が遊びに来た。
「こんにちは」
痩せてメガネをかけたお兄ちゃんは「小石です」と名乗ってぼくの頭を撫でてくれた。
「思ったよりもずっと可愛いじゃん」
小石さんはそう笑ってお兄ちゃんに相づちをうっているのが見えた。可愛いと言いわれるのは大好きだったので悪い気はしなかった。小石さんはカバンからカメラを取り出して、ぼくに見せて来た。
「何か知ってる?」
「カメラでしょ?それくらい知ってるよ」
ぼくは自信満々に答えた。けれど、デジタルカメラは見るのが初めてだった。見てるだけでも夢中になった。
「うん。今日は一路くん撮りに来たんだよ。な、そうだよな」
「ああ」とお兄ちゃん小石さんに相づちをうつ。
「ぼくを?本当?」
嬉しくなってぼくは一人でばたばた飛び回る。そして満面の笑顔でお兄ちゃんと小石さんに尋ねた。
「ねっ。それで、何を撮るの?」
んー。と小石さんはちょっとの間考える振りをしてみせ、そして少しして何かお気に入りのポーズとかある?と、僕に尋ねて来た。
ポーズ?と言われてもなかなかすぐには動けない。カメラを向けられたままモジモジしていると、お兄ちゃんが呑気な口調でぼくに声をかけた。
「一路、いつものやつやれよ」
「いつもの?」
ぼくは眉をひそめる。いつものって?と聞いた。
「しんちゃんのマネ。一路、大好きだからな。振り付け完璧なんだよな」
「そうなのかー。そりゃいい」
小石さんは大げさに驚いた様な声をあげて、歯を見せて笑みを向けた。
「しんちゃんのマネってさ。例えばどんなことだい?」
「ちょっとーお兄ちゃん。お母さんに怒られるよ!」
見つかったらどうなるかは想像するだけで怖かった。もしかしたら夏休みの間外出禁止を食らうかもしれない。けれど、怒ってもお兄ちゃんはヘラヘラと笑ってみるだけだ。
「はは。いいだろ。お母さんには内緒だって。約束するよ」
「やだよ。去年、お兄ちゃんのせーで、お尻打たれたもん!」
「お前も飴なんかでつられるからだろ?」
お互いにらみ合っていると小石さんが手を打って仲へ入って来た。
「な。いいアイディアあるんだけどさ。お前と一路くんが二人とも互いの母ちゃんには言わないって約束すればいいんだろ?」
「ん?ああ。別にこのデブちんが破らなけりゃ問題ないさ」
「ぼくも、兄ちゃんが破らなけりゃ問題ないもん」
意地を張って太い腕を無理矢理組んでいると小石さんはバッグから一枚の紙を取り出した。
何これ。とぼくの問いに、小石さんはいいからいいから。とそこに何かを書き込んでいく。
まだ習った事の無い漢字がそこにずらっと並ぶ。
「一路くん、これ読める?」
ぼくは首を振る。
契約書、とお兄ちゃんが代わりに答えた。何それ。とぼくは首を傾げる。
ただ、誰かに構って欲しかっただけだったと思う。実際、性格は内向的で、人見知りは山ほどした。
近所の友達はみんな大人しい子が揃っていて、ぼくは彼らを盛り上げ役を務めていた。夏は川の中に服のまま飛び込んで馬鹿をして彼らを笑わせたりと、やりたい放題の日常を送っていた。
そんなぼくには従兄弟のお兄ちゃんがいて、夏休みになると毎年、お兄さんの家に遊びに行った。お兄ちゃんは大分年が離れているけれど、ぼくのことをすごく可愛がってくれた。
「一路はドラ◯もんみたいで可愛いな〜」
お兄ちゃんはそう言いながらぼくを膝の上に乗せて頭を撫でてくれた。ぼくも甘えるのが大好きだったので、お兄ちゃんの膝の上で調子のいい事をいいながら、お兄ちゃんを笑わせていた。お兄ちゃんの膝の上で寝てしまう事だって何度かあったくらいだ。
そんなお兄ちゃんが笑ってくれるのが大好きだったぼくは、お兄ちゃんが笑ってくれるなら何でもした。テレビのしんちゃんのようにケツだけ星人をやったり、ちんちんにゾウサンを描いて踊ったりもした。大抵パンツを脱ぐとお兄ちゃんは喜んで褒美にお菓子をくれるので、お兄ちゃんの前ではパンツを脱ぐのは当たり前になっていたんだと思う。
暇になるとぼくはいつも裸でおちんちんを突き出してみせた。もちろん、お兄ちゃんのお母さんに見つかると、ぼくのお母さんに報告されて痛い目にあった。
そして、そんなある年の夏の日ことだった。ぼくが小学三年生になる頃のこと。
お兄ちゃんと二人でお兄ちゃんの家でゲームをしていると、珍しくお兄ちゃんの友達が遊びに来た。
「こんにちは」
痩せてメガネをかけたお兄ちゃんは「小石です」と名乗ってぼくの頭を撫でてくれた。
「思ったよりもずっと可愛いじゃん」
小石さんはそう笑ってお兄ちゃんに相づちをうっているのが見えた。可愛いと言いわれるのは大好きだったので悪い気はしなかった。小石さんはカバンからカメラを取り出して、ぼくに見せて来た。
「何か知ってる?」
「カメラでしょ?それくらい知ってるよ」
ぼくは自信満々に答えた。けれど、デジタルカメラは見るのが初めてだった。見てるだけでも夢中になった。
「うん。今日は一路くん撮りに来たんだよ。な、そうだよな」
「ああ」とお兄ちゃん小石さんに相づちをうつ。
「ぼくを?本当?」
嬉しくなってぼくは一人でばたばた飛び回る。そして満面の笑顔でお兄ちゃんと小石さんに尋ねた。
「ねっ。それで、何を撮るの?」
んー。と小石さんはちょっとの間考える振りをしてみせ、そして少しして何かお気に入りのポーズとかある?と、僕に尋ねて来た。
ポーズ?と言われてもなかなかすぐには動けない。カメラを向けられたままモジモジしていると、お兄ちゃんが呑気な口調でぼくに声をかけた。
「一路、いつものやつやれよ」
「いつもの?」
ぼくは眉をひそめる。いつものって?と聞いた。
「しんちゃんのマネ。一路、大好きだからな。振り付け完璧なんだよな」
「そうなのかー。そりゃいい」
小石さんは大げさに驚いた様な声をあげて、歯を見せて笑みを向けた。
「しんちゃんのマネってさ。例えばどんなことだい?」
「ちょっとーお兄ちゃん。お母さんに怒られるよ!」
見つかったらどうなるかは想像するだけで怖かった。もしかしたら夏休みの間外出禁止を食らうかもしれない。けれど、怒ってもお兄ちゃんはヘラヘラと笑ってみるだけだ。
「はは。いいだろ。お母さんには内緒だって。約束するよ」
「やだよ。去年、お兄ちゃんのせーで、お尻打たれたもん!」
「お前も飴なんかでつられるからだろ?」
お互いにらみ合っていると小石さんが手を打って仲へ入って来た。
「な。いいアイディアあるんだけどさ。お前と一路くんが二人とも互いの母ちゃんには言わないって約束すればいいんだろ?」
「ん?ああ。別にこのデブちんが破らなけりゃ問題ないさ」
「ぼくも、兄ちゃんが破らなけりゃ問題ないもん」
意地を張って太い腕を無理矢理組んでいると小石さんはバッグから一枚の紙を取り出した。
何これ。とぼくの問いに、小石さんはいいからいいから。とそこに何かを書き込んでいく。
まだ習った事の無い漢字がそこにずらっと並ぶ。
「一路くん、これ読める?」
ぼくは首を振る。
契約書、とお兄ちゃんが代わりに答えた。何それ。とぼくは首を傾げる。