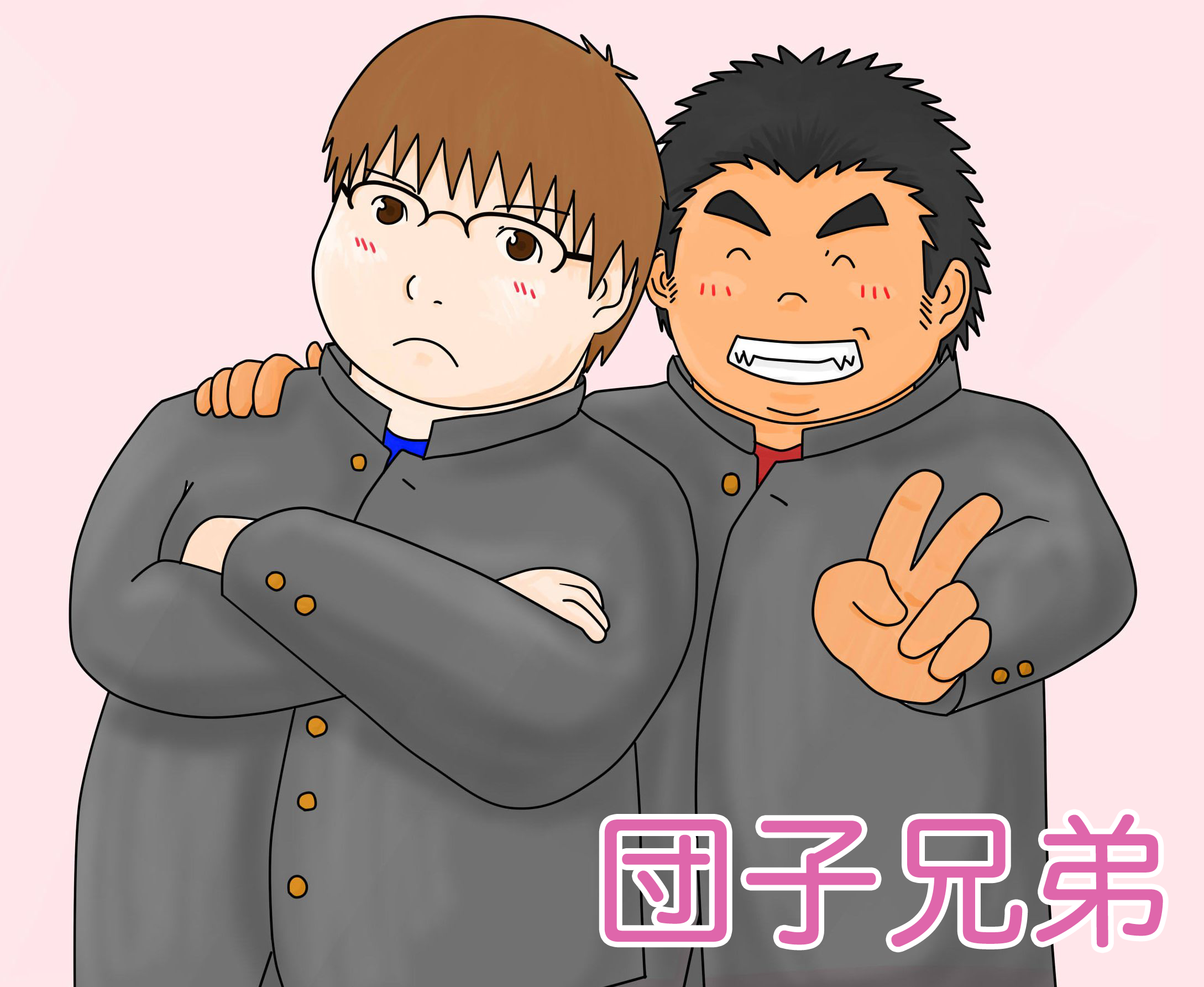赤ちゃん撮影
『知り合いでさ、プロの映画監督志望の人いるんだけど…お前、役者やってみる?』
「え?」
トイレで用を足し終えたところだった。大川耕太は顔を上げて隣の少年を見つめる。彼の名は晴彦と言った。あまり喋った事はなかったが、挨拶程度ならしたことはあるので、名前は知っていた。
「ぼくが?」
「ああ」
晴彦は素っ気なく頷いた。
「俺が紹介したんだ。学校で俳優になってみたいって言ってる子がいるってさ。連れて来てくれって」
彼の顔は大真面目だ。鳥肌が一気に立つのを感じた。そう。大川耕太は太っちょの体型に似合わず、生まれながらの俳優志望だったのだ。
「いいの?いいの?」
手も洗わずと子犬の様に晴彦へと飛びつく。
「うん。ただ、最初に審査あるけどな。そこで、通ればだぞ」
念を押したように彼は言った。「それでもやるか?」
「やるやる!」
嬉しくなってぼくはトイレの中ではしゃぎ回った。
それがぼくの人生を変えてしまうことも知らずに…。
その日。さっそくぼくは晴彦に着いてある場所へ向かった。
古びた施設のような所だった。自転車を止めて、晴彦とともに靴のまま中に入った。
「昨日眠れたか?」
「もちろん」
もちろん、眠れる訳がなかった。ずっと願って来た夢が今現実になりそうなのに…。ぼくは嬉しさで一晩中興奮して寝返りをうっていた。
「耕太、タフそうだからな」
「でしょ?」
「体型的にもな」
「まーね」
笑ったが、内心ちょっとムカッとする。体型の事は結構気にしていた。
階段を上がったところ直ぐ右に入り口があり、中に入った。ちょっと小さめのコンサート上の様なところだ。客席があり、舞台がある。
「すげー!」
「あそこで、演技するんだぜ?できる?」
「うん!楽しみ!」
胸の鼓動はますます高鳴った。
とりあえず、ぼくと晴彦は客席で座って待った。
「早く来すぎた?」
誰もいないホールを見渡しながらぼくが言うと、当たり前のように彼はこう言った。
「早く来た方がポイント高いだろ?」
「なるほどね」
時間があるうちにぼくは晴彦にいろいろな事を尋ねた。
妙に詳しい晴彦は、まず「おどおどしないこと」とぼくに忠告した。
それなら大丈夫かもしれない。常にぼくは自信家だ。そうでなければ、俳優になりたいなんて堂々と発表できるはずがない。
「あとは?」と訊くと、「それだけ」と言われた。
「演技のコツとか…いちお、初心者だし」
「別にそんなんいらねーよ。恥ずかしがらなきゃ初心者だって変わんないさ」
へー。と納得したように頷いた。一理あるかもしれない。大勢の前でどんな演技をさせられるのだろう。そしてやはり、最初の審査も演技のテストなのだろうか。
いろいろと疑問が浮かぶ。いつの間にか集合時間となり、大勢の人が中に入って来た。
「立って」と晴彦がぼくに言ってぼくは立ち上がる。
帽子を深く被り、ヒゲを生やしサングラスをかけたお兄さんが舞台に上がって指示をだしている。年は二十代くらいだろうか…、見た目からして監督だと分かった。
晴彦はぼくをその人の前まで連れて行ってくれた。舞台へ上がってぼくらは男の人の前に並んだ。
「ん?」
男は振り返った。
「小石さん、この子。前言ってたこですよ」
「へ〜」と、監督らしき男は、ぼくの体をじっくりと見つめる。
「面白いな。晴彦、本当にお前の言った通りだな」
少し薄ら笑いをした表情は気に障ったがぼくは元気よく自己紹介をして頭を下げた。
「耕太くんだね。元気そうで何より」
「はい!よろしくお願いします!」
またぼくは頭を深く下げる。
「へ〜」
ぼくの挨拶を聞いていた数人の大人の人が笑った。ちょっと恥ずかしくなってキョロキョロすると「おどおどするな」と晴彦に耳打ちされた。
「体重は?」
「40キロです!ってのは嘘で、60キロです」
体重の事で笑いを取りたくはなかったが、仕方がなかった。でもお陰で、ちょっとだけ周りが笑ってくれた。
「冗談も上手いなぁ。耕太くん、緊張とかしないの?」
「全然です」
脇の下の汗はびっしょりだ。
「んじゃ、最初はちょっと演技のテストしてもらおうかな」
小石さんはそう言ってぼくに一枚のプリントを差し出した。
「そこにテスト内容書いてあるから、目通して。テストは、3分後かな」
時計をちらっと見て舞台の方へとすぐに行ってしまう。ぼく席に戻って、はプリントを見つめた。
《赤ん坊の演技》
「赤ん坊??マジで?」
思わぬ難題に戸惑ってしまう。
「簡単でよかったじゃん」と晴彦はぼくの肩を叩いた。
「でもさあ。みんなの前でやるの?これ?」
確かに何か実際にあるものを演技することはぼくだって予想できた。ただ、まさか赤ん坊だとは思ってもいなかったのだ。
「お前、やる気あんの?」
晴彦はちょっと怖い顔をぼくに向けた。
「いや、あるよ。あるある」
慌てて言ってぼくは頭の中でシュミレーションする。
「演技の練習しなくていいの?」と晴彦。
「いや、まあ…」
ぼくはのそっと立ち上がった。大人の人たちはみんなバタバタしていてこちらなんて気にしていない。晴彦だけがぼくをジッと見つめている。
「ん〜」
ぼくは腰を下ろして、指をくわえた。
「だぁっだぁ!」
と両手両足をバタバタさせる。
「どう?」
そう訊きながら顔は真っ赤だった。
「声小さいだろ」
真顔で晴彦はぼくに言い放った。
「それじゃ、俺なら落とすぜ」
「わ、わかったよ…」
ぼくはまたしゃがんで、指をくわえて、「だあ。だあ」と泣くマネをした。今度は寝転がって本当の赤ん坊のように振る舞った。
しかし、これを同級生の前でやるのは相当恥ずかしかった。
「いいね」
真っ赤な顔をしているぼくに晴彦は拍手を送った。
「お前、顔赤ちゃんみたいだから。結構いけてるかも。幼児体系だし、それに手足も短いしな」
「そ、そう…?」
あんまり嬉しくなかった。むしろ恥ずかしく、腹ただしい。
すると笛の音がする。
——小石さんだ。
ぼくは立ち上がって舞台に上がり、小石さんの前に立った。
「準備いいか?」
「…はい」
唾を呑み込んでそう言うと、小石さんは「始めるぞ」と大勢の人に行って全員を舞台から下ろす。もちろん小石さんも客席の方へと向かった。
舞台へ立っているのは自分だけとなる。途端に緊張感が漂う。
「じゃあ、いくぞー」
メガホンを持った小石さんがぼくに指示した。
「3、2、1、アクション!」
ぼくは舞台の上でお尻を下ろして、指をくわえ大勢の前で「だあ、だあ」と泣き声を上げた。誰も笑わなかった。重い空気だけがひたすら漂う。
演技は十秒も持たなかった。そもそも赤ん坊の役に三分しか与えられなかった中学生のぼくはそれくらいしか思いつかなかったのだ。
立ち上がると、「終わり?」と訊かれた。コクンと頷く。
「デブ太くんだっけ?」
「耕太です」
キツい冗談に少し周りの人が笑った。舞台の真ん中でぼくはちょっとお腹を引っ込める。
「俳優志望だったよね?」
「は、はい!」
「やる気あるの?」
「…あ、あります」
慌てながらぼくは答える。右列の席の晴彦を見ると険しい表情でぼくを見ていた。
「ん〜。困ったな…。晴くんの紹介で期待してたんだけどね…正直、期待はずれ」
「……すみません」
モジモジしていると「もう、いいよ」と言われ舞台から下ろされた。
「俺のメンツ台無し」
席へ戻ると晴彦がそう言ってぼくを睨んだ。
「ご…めん」
ぼくは頭を下げる。もう何だか、何と言っていいか分からなかった。
「これで、終わり?」
泣きそうな顔で尋ねると「終わり」とあっさり言われる。
「え…でも…」
「仕方ないだろ。お前がしくじったんだから」
「…頼むよ、もう一回さ。ぼく、頑張るから」
必死で晴彦に頼むと、晴彦は大きなため息をついてぼくをもう一度小石さんの前に連れて行った。
二人で頭を下げる。
「すみませんでした!」
「……で?だから、何?」
冷たい口調で小石さんはぼくに尋ねた。
「ぼ、ぼくに、もう一度、やらせてください!」
「んー」
ちょっと考えるように小石さんは腕を組む。
「プロ志望なら一回で成功させるのが当たり前なんだけどねぇ」
「……」
ぼくは顔を俯かせる。後悔が襲ってくる。必死に心の中で手を合わせた。
すると、小石さんは納得したように頷いて顔を上げるように指示した。
「ま、晴くんの友人なら仕方ないか。もう一回、チャンスあげるか」
「ありがとうございます!」
ぼくは頭を下げる。
「ただ、練習なし。今、始めな」
「今ですか?」
「ああ。今、だ。俺の造る映画はアドリブってのを大切にしててね。これくらいできなきゃ、正直これから使えないんだよね…どうする?」
晴彦と目を合わせた。じっとぼくの瞳を見つめている。迷っている時間はなかった。
「やります!!」
「任せた」
小石さんはぼくの頭を二、三度、軽く叩いて微笑んでくれた。
「頑張ってね」と、近くのの女の人もぼくに笑いかけてくれる。ぼくは頷いて舞台へ上がった。
「では。行くぞ、デブタくん」
「はい……耕太です!」
笑いが聞こえた。少し体が軽くなる。
赤ん坊を想像する。何をしているのか…??
(本物の赤ん坊になるんだ)
「3、2、1、アクション!」
ぼくは手と肘を床に着いて四つん這いの格好になった。
「だあ、だあ」と言いながらよたよたと這い回る。
「あ、いいね〜」と小石さんの声が聞こえる。
足を滑らせて仰向けに転がって「だあ、だあ」と泣きまねをした。
「カット!」と声が聞こえる。
ぼくは立ち上がった。途端に大勢の人たちがぼくに拍手をくれた。照れくさくなってぼくは頭を掻いた。
「よかったよ〜!」小石さんが立ち上がってそう言う。
「い、いや。ありがとうございます」
「うん。本当の赤ん坊みたいだった。うんうん。じゃあ、次は…おい、千香ちゃん」
千香と呼ばれた女の人が立ち上がって舞台に上がってくる。手には小さな袋を下げていた。
「これ、つけて」
「……??」
ぼくは目を点にした。彼女が袋から出したものは涎掛けや、おしゃぶり、さらにおしめまで出てくる。
「…はい?」
「だから、これ付けてって」
「あの…どれですか?」
「全部よ?」
当然のような口調で言われる。
「いや……でも」
「もう、モジモジしないの!」
怒ったように言われる。ぼくが黙るとさっそく千香さんはぼくのシャツに手をかけた。
「え?え?え?」
シャツが捲れて大きなお腹が露になる。
「…え、あの…」
胸まで見える。上半身裸になると自然と顔が赤くなった。
「おっぱいでけー」
見れば客席で晴彦がぼくの上半身を見てニヤニヤしていた。恥ずかしくなり、胸と隠そうとすると「君、オカマか?」と客席の男の人から言われて、大勢に笑われてしまった。
後ろから手が伸びぼくの首に涎掛けをつけられた。
「似合ってるね〜」と小石さんの声といくつかの笑い声が聞こえた。
大勢の前で涎掛けなんて付けられ、正直死にたい気分だ。
「じゃあ。下もね」
千香さんがぼくのズボンに手をかけた。
「え?でも…それは」
「だから、モジモジしないの。俳優になるんでしょ?恥ずかしがっちゃダメよ」
するっとズボンを下ろされる。舞台の上で、ぼくはブリーフが一丁になってしまう。
「やだー、かわい〜」
他の女の人が客席でそう言うのが聞こえた。
「最近の中学生ってブリーフ履いてるのか?」
「いや、トランクスでしょ?ふつー」
晴彦の楽しそうな声が聞こえる。ぼくだってそりゃ、トランクスを履きたい。けれどお母さんが未だに買ってくれないのだ。
「じゃあ、パンツだね」
千香さんの手がぼくのパンツに伸びる。ぼくは腰を引っ込めた。
「む、無理です…」
「え?どうして?」
小石さんが不思議そうにぼくを見つめる。
「赤ちゃんを演じるだけなんだぞ。俳優志望が、これくらいのことできないでどうする?」
「で、でも…」
「どうなんだ?やるのか、やらないのか。やらないなら、ここで終わりだぞ?」
そう、厳しく言われ、ぼくは黙った。晴彦の方を見つめる。じーっとぼくを冷たい視線で見つめている。口で「やれ」と言っているのが見えた。
確かに、今このチャンスを逃したら、もう後がないのかもしれない。晴彦だってぼくの夢を応援したいからぼくを誘ってくれたんだし…。
ぼくは拳を握りしめた。そして大きく頷いた。
「ぬ、脱ぎます」
ぼくは後ろを向いて自らパンツを下ろした。お尻が出ると「ケツ、ケツ!」と晴彦の興奮した声が聞こえた。
「奇麗なお尻だね〜」
「大きいな〜」
「プリプリしとるな〜」
半ば冷やかしの声まで聞こえる。ブリーフを足から抜き取り、客席の方へお尻を向けたまま泣きそうな表情で途方に暮れていると、千香さんがぼくの手を引いてゆっくり体を仰向けにした。ぼくは股間に両手を添える。
「あ…あ…」と呟いていると口におしゃぶりを入れられた。
「オムツつけてあげるから」
「…ん…」
「ほら、手どけて、足上げて」
しぶしぶ手をどける。ぼくの小さなアソコが千香さんの前で露になった。
ぼくのアソコの毛はまだ生えていなかった。そしてもの凄く小さかった。それは太った体型の次にコンプレックスだった。勃起しても皮は剥けず、通常は金玉に隠れて遠くからじゃあるかどうかもわからないくらいだ。
「あーかわいい」
千香さんが大きな声で言った。幸運にも客席からじゃ仰向けのぼくの股間は見えない。
けれど、小石さんはわざとぼくにとって恥ずかしい質問を千香さんぶつけた。
「おーい、千香ちゃん、かわいいって、小さいって意味か?ひょっとして、生えてねーのか?」
ぼくの顔が引きつる。
「監督ー、ダメですよ。恥ずかしがってる子いじめちゃ」
千香さんがぼくの泣きそうな顔を確認しながらそう言った。
「馬鹿、恥ずかしがってて、役者が勤まるかよ」
小石さんはそう言う。けれど、その口元はニヤツいていた。全裸に、涎掛けをかけ、おしゃぶりをつけて横たわっているぼくが相当可笑しいと言った表情だ。
「サイズ教えてよーサイズ」
今度は晴彦がそう席から言う。
一度放した手をぼくはアソコに戻そうとする。
オムツでも何でもいいから早く履かせて欲しかった。女の人の前でこの状態でいるのは死ぬ程恥ずかしい。
「もー、晴くんまで、やーねー」と、千香さんはいいながらもぼくの股間の長さを伝えるかのように、親指と人差し指で、「これくらいかな」とぼくのアソコのサイズを作った。意地悪なのか、親指と人差し指をくっつきそうなくらい寄せている。
「あわわ、ちっさーーーーー!!」と、晴彦。
大勢の人が笑った。顔がリンゴのように熱く、赤くなる。
笑いながら千香さんはぼくの両足を掴んで上に上げた。誰にも見られた事のないお尻の穴や玉の裏側が千香さんに向けられる。涙が出そうになる。
「よし、完成!」
オムツを完全に履かされると。ぼくは手を引いて立ち上がらされた。もちろん涎掛けにおしゃぶりをして、オムツの状態だ。
途端に客席からクスクス笑い声が聞こえる。
「本物の赤ちゃんみたいだね」と千香さんはそれだけ言って客席へ戻った。
「うん。確かに似合ってるな」
小石さんは真面目に頷く。
「それにしても、大きな赤ちゃんだな」と一言付け加える。ぼくの顔がまた赤くなる。
「よし、じゃあそれで演技をしてみようか」
もう頷くしかなかった。涙目になりながらぼくはさっきの演技をやらされた。
本物のオムツをして舞台を這い回るぼくは情けなくて仕方なかった。客席でもたまに押し殺したような笑い声が聞こえて、ぼくの羞恥心は高まった。
だぁ。だぁ。
「そこで泣いて。あ、もう涙目みたいだね。いやーキミ最高だよー!」
小石さんの嬉しそうな声が聞こえる。目に涙を浮かべながらぼくはもう一度声を上げた。
だぁ。だぁ。
「え?」
トイレで用を足し終えたところだった。大川耕太は顔を上げて隣の少年を見つめる。彼の名は晴彦と言った。あまり喋った事はなかったが、挨拶程度ならしたことはあるので、名前は知っていた。
「ぼくが?」
「ああ」
晴彦は素っ気なく頷いた。
「俺が紹介したんだ。学校で俳優になってみたいって言ってる子がいるってさ。連れて来てくれって」
彼の顔は大真面目だ。鳥肌が一気に立つのを感じた。そう。大川耕太は太っちょの体型に似合わず、生まれながらの俳優志望だったのだ。
「いいの?いいの?」
手も洗わずと子犬の様に晴彦へと飛びつく。
「うん。ただ、最初に審査あるけどな。そこで、通ればだぞ」
念を押したように彼は言った。「それでもやるか?」
「やるやる!」
嬉しくなってぼくはトイレの中ではしゃぎ回った。
それがぼくの人生を変えてしまうことも知らずに…。
その日。さっそくぼくは晴彦に着いてある場所へ向かった。
古びた施設のような所だった。自転車を止めて、晴彦とともに靴のまま中に入った。
「昨日眠れたか?」
「もちろん」
もちろん、眠れる訳がなかった。ずっと願って来た夢が今現実になりそうなのに…。ぼくは嬉しさで一晩中興奮して寝返りをうっていた。
「耕太、タフそうだからな」
「でしょ?」
「体型的にもな」
「まーね」
笑ったが、内心ちょっとムカッとする。体型の事は結構気にしていた。
階段を上がったところ直ぐ右に入り口があり、中に入った。ちょっと小さめのコンサート上の様なところだ。客席があり、舞台がある。
「すげー!」
「あそこで、演技するんだぜ?できる?」
「うん!楽しみ!」
胸の鼓動はますます高鳴った。
とりあえず、ぼくと晴彦は客席で座って待った。
「早く来すぎた?」
誰もいないホールを見渡しながらぼくが言うと、当たり前のように彼はこう言った。
「早く来た方がポイント高いだろ?」
「なるほどね」
時間があるうちにぼくは晴彦にいろいろな事を尋ねた。
妙に詳しい晴彦は、まず「おどおどしないこと」とぼくに忠告した。
それなら大丈夫かもしれない。常にぼくは自信家だ。そうでなければ、俳優になりたいなんて堂々と発表できるはずがない。
「あとは?」と訊くと、「それだけ」と言われた。
「演技のコツとか…いちお、初心者だし」
「別にそんなんいらねーよ。恥ずかしがらなきゃ初心者だって変わんないさ」
へー。と納得したように頷いた。一理あるかもしれない。大勢の前でどんな演技をさせられるのだろう。そしてやはり、最初の審査も演技のテストなのだろうか。
いろいろと疑問が浮かぶ。いつの間にか集合時間となり、大勢の人が中に入って来た。
「立って」と晴彦がぼくに言ってぼくは立ち上がる。
帽子を深く被り、ヒゲを生やしサングラスをかけたお兄さんが舞台に上がって指示をだしている。年は二十代くらいだろうか…、見た目からして監督だと分かった。
晴彦はぼくをその人の前まで連れて行ってくれた。舞台へ上がってぼくらは男の人の前に並んだ。
「ん?」
男は振り返った。
「小石さん、この子。前言ってたこですよ」
「へ〜」と、監督らしき男は、ぼくの体をじっくりと見つめる。
「面白いな。晴彦、本当にお前の言った通りだな」
少し薄ら笑いをした表情は気に障ったがぼくは元気よく自己紹介をして頭を下げた。
「耕太くんだね。元気そうで何より」
「はい!よろしくお願いします!」
またぼくは頭を深く下げる。
「へ〜」
ぼくの挨拶を聞いていた数人の大人の人が笑った。ちょっと恥ずかしくなってキョロキョロすると「おどおどするな」と晴彦に耳打ちされた。
「体重は?」
「40キロです!ってのは嘘で、60キロです」
体重の事で笑いを取りたくはなかったが、仕方がなかった。でもお陰で、ちょっとだけ周りが笑ってくれた。
「冗談も上手いなぁ。耕太くん、緊張とかしないの?」
「全然です」
脇の下の汗はびっしょりだ。
「んじゃ、最初はちょっと演技のテストしてもらおうかな」
小石さんはそう言ってぼくに一枚のプリントを差し出した。
「そこにテスト内容書いてあるから、目通して。テストは、3分後かな」
時計をちらっと見て舞台の方へとすぐに行ってしまう。ぼく席に戻って、はプリントを見つめた。
《赤ん坊の演技》
「赤ん坊??マジで?」
思わぬ難題に戸惑ってしまう。
「簡単でよかったじゃん」と晴彦はぼくの肩を叩いた。
「でもさあ。みんなの前でやるの?これ?」
確かに何か実際にあるものを演技することはぼくだって予想できた。ただ、まさか赤ん坊だとは思ってもいなかったのだ。
「お前、やる気あんの?」
晴彦はちょっと怖い顔をぼくに向けた。
「いや、あるよ。あるある」
慌てて言ってぼくは頭の中でシュミレーションする。
「演技の練習しなくていいの?」と晴彦。
「いや、まあ…」
ぼくはのそっと立ち上がった。大人の人たちはみんなバタバタしていてこちらなんて気にしていない。晴彦だけがぼくをジッと見つめている。
「ん〜」
ぼくは腰を下ろして、指をくわえた。
「だぁっだぁ!」
と両手両足をバタバタさせる。
「どう?」
そう訊きながら顔は真っ赤だった。
「声小さいだろ」
真顔で晴彦はぼくに言い放った。
「それじゃ、俺なら落とすぜ」
「わ、わかったよ…」
ぼくはまたしゃがんで、指をくわえて、「だあ。だあ」と泣くマネをした。今度は寝転がって本当の赤ん坊のように振る舞った。
しかし、これを同級生の前でやるのは相当恥ずかしかった。
「いいね」
真っ赤な顔をしているぼくに晴彦は拍手を送った。
「お前、顔赤ちゃんみたいだから。結構いけてるかも。幼児体系だし、それに手足も短いしな」
「そ、そう…?」
あんまり嬉しくなかった。むしろ恥ずかしく、腹ただしい。
すると笛の音がする。
——小石さんだ。
ぼくは立ち上がって舞台に上がり、小石さんの前に立った。
「準備いいか?」
「…はい」
唾を呑み込んでそう言うと、小石さんは「始めるぞ」と大勢の人に行って全員を舞台から下ろす。もちろん小石さんも客席の方へと向かった。
舞台へ立っているのは自分だけとなる。途端に緊張感が漂う。
「じゃあ、いくぞー」
メガホンを持った小石さんがぼくに指示した。
「3、2、1、アクション!」
ぼくは舞台の上でお尻を下ろして、指をくわえ大勢の前で「だあ、だあ」と泣き声を上げた。誰も笑わなかった。重い空気だけがひたすら漂う。
演技は十秒も持たなかった。そもそも赤ん坊の役に三分しか与えられなかった中学生のぼくはそれくらいしか思いつかなかったのだ。
立ち上がると、「終わり?」と訊かれた。コクンと頷く。
「デブ太くんだっけ?」
「耕太です」
キツい冗談に少し周りの人が笑った。舞台の真ん中でぼくはちょっとお腹を引っ込める。
「俳優志望だったよね?」
「は、はい!」
「やる気あるの?」
「…あ、あります」
慌てながらぼくは答える。右列の席の晴彦を見ると険しい表情でぼくを見ていた。
「ん〜。困ったな…。晴くんの紹介で期待してたんだけどね…正直、期待はずれ」
「……すみません」
モジモジしていると「もう、いいよ」と言われ舞台から下ろされた。
「俺のメンツ台無し」
席へ戻ると晴彦がそう言ってぼくを睨んだ。
「ご…めん」
ぼくは頭を下げる。もう何だか、何と言っていいか分からなかった。
「これで、終わり?」
泣きそうな顔で尋ねると「終わり」とあっさり言われる。
「え…でも…」
「仕方ないだろ。お前がしくじったんだから」
「…頼むよ、もう一回さ。ぼく、頑張るから」
必死で晴彦に頼むと、晴彦は大きなため息をついてぼくをもう一度小石さんの前に連れて行った。
二人で頭を下げる。
「すみませんでした!」
「……で?だから、何?」
冷たい口調で小石さんはぼくに尋ねた。
「ぼ、ぼくに、もう一度、やらせてください!」
「んー」
ちょっと考えるように小石さんは腕を組む。
「プロ志望なら一回で成功させるのが当たり前なんだけどねぇ」
「……」
ぼくは顔を俯かせる。後悔が襲ってくる。必死に心の中で手を合わせた。
すると、小石さんは納得したように頷いて顔を上げるように指示した。
「ま、晴くんの友人なら仕方ないか。もう一回、チャンスあげるか」
「ありがとうございます!」
ぼくは頭を下げる。
「ただ、練習なし。今、始めな」
「今ですか?」
「ああ。今、だ。俺の造る映画はアドリブってのを大切にしててね。これくらいできなきゃ、正直これから使えないんだよね…どうする?」
晴彦と目を合わせた。じっとぼくの瞳を見つめている。迷っている時間はなかった。
「やります!!」
「任せた」
小石さんはぼくの頭を二、三度、軽く叩いて微笑んでくれた。
「頑張ってね」と、近くのの女の人もぼくに笑いかけてくれる。ぼくは頷いて舞台へ上がった。
「では。行くぞ、デブタくん」
「はい……耕太です!」
笑いが聞こえた。少し体が軽くなる。
赤ん坊を想像する。何をしているのか…??
(本物の赤ん坊になるんだ)
「3、2、1、アクション!」
ぼくは手と肘を床に着いて四つん這いの格好になった。
「だあ、だあ」と言いながらよたよたと這い回る。
「あ、いいね〜」と小石さんの声が聞こえる。
足を滑らせて仰向けに転がって「だあ、だあ」と泣きまねをした。
「カット!」と声が聞こえる。
ぼくは立ち上がった。途端に大勢の人たちがぼくに拍手をくれた。照れくさくなってぼくは頭を掻いた。
「よかったよ〜!」小石さんが立ち上がってそう言う。
「い、いや。ありがとうございます」
「うん。本当の赤ん坊みたいだった。うんうん。じゃあ、次は…おい、千香ちゃん」
千香と呼ばれた女の人が立ち上がって舞台に上がってくる。手には小さな袋を下げていた。
「これ、つけて」
「……??」
ぼくは目を点にした。彼女が袋から出したものは涎掛けや、おしゃぶり、さらにおしめまで出てくる。
「…はい?」
「だから、これ付けてって」
「あの…どれですか?」
「全部よ?」
当然のような口調で言われる。
「いや……でも」
「もう、モジモジしないの!」
怒ったように言われる。ぼくが黙るとさっそく千香さんはぼくのシャツに手をかけた。
「え?え?え?」
シャツが捲れて大きなお腹が露になる。
「…え、あの…」
胸まで見える。上半身裸になると自然と顔が赤くなった。
「おっぱいでけー」
見れば客席で晴彦がぼくの上半身を見てニヤニヤしていた。恥ずかしくなり、胸と隠そうとすると「君、オカマか?」と客席の男の人から言われて、大勢に笑われてしまった。
後ろから手が伸びぼくの首に涎掛けをつけられた。
「似合ってるね〜」と小石さんの声といくつかの笑い声が聞こえた。
大勢の前で涎掛けなんて付けられ、正直死にたい気分だ。
「じゃあ。下もね」
千香さんがぼくのズボンに手をかけた。
「え?でも…それは」
「だから、モジモジしないの。俳優になるんでしょ?恥ずかしがっちゃダメよ」
するっとズボンを下ろされる。舞台の上で、ぼくはブリーフが一丁になってしまう。
「やだー、かわい〜」
他の女の人が客席でそう言うのが聞こえた。
「最近の中学生ってブリーフ履いてるのか?」
「いや、トランクスでしょ?ふつー」
晴彦の楽しそうな声が聞こえる。ぼくだってそりゃ、トランクスを履きたい。けれどお母さんが未だに買ってくれないのだ。
「じゃあ、パンツだね」
千香さんの手がぼくのパンツに伸びる。ぼくは腰を引っ込めた。
「む、無理です…」
「え?どうして?」
小石さんが不思議そうにぼくを見つめる。
「赤ちゃんを演じるだけなんだぞ。俳優志望が、これくらいのことできないでどうする?」
「で、でも…」
「どうなんだ?やるのか、やらないのか。やらないなら、ここで終わりだぞ?」
そう、厳しく言われ、ぼくは黙った。晴彦の方を見つめる。じーっとぼくを冷たい視線で見つめている。口で「やれ」と言っているのが見えた。
確かに、今このチャンスを逃したら、もう後がないのかもしれない。晴彦だってぼくの夢を応援したいからぼくを誘ってくれたんだし…。
ぼくは拳を握りしめた。そして大きく頷いた。
「ぬ、脱ぎます」
ぼくは後ろを向いて自らパンツを下ろした。お尻が出ると「ケツ、ケツ!」と晴彦の興奮した声が聞こえた。
「奇麗なお尻だね〜」
「大きいな〜」
「プリプリしとるな〜」
半ば冷やかしの声まで聞こえる。ブリーフを足から抜き取り、客席の方へお尻を向けたまま泣きそうな表情で途方に暮れていると、千香さんがぼくの手を引いてゆっくり体を仰向けにした。ぼくは股間に両手を添える。
「あ…あ…」と呟いていると口におしゃぶりを入れられた。
「オムツつけてあげるから」
「…ん…」
「ほら、手どけて、足上げて」
しぶしぶ手をどける。ぼくの小さなアソコが千香さんの前で露になった。
ぼくのアソコの毛はまだ生えていなかった。そしてもの凄く小さかった。それは太った体型の次にコンプレックスだった。勃起しても皮は剥けず、通常は金玉に隠れて遠くからじゃあるかどうかもわからないくらいだ。
「あーかわいい」
千香さんが大きな声で言った。幸運にも客席からじゃ仰向けのぼくの股間は見えない。
けれど、小石さんはわざとぼくにとって恥ずかしい質問を千香さんぶつけた。
「おーい、千香ちゃん、かわいいって、小さいって意味か?ひょっとして、生えてねーのか?」
ぼくの顔が引きつる。
「監督ー、ダメですよ。恥ずかしがってる子いじめちゃ」
千香さんがぼくの泣きそうな顔を確認しながらそう言った。
「馬鹿、恥ずかしがってて、役者が勤まるかよ」
小石さんはそう言う。けれど、その口元はニヤツいていた。全裸に、涎掛けをかけ、おしゃぶりをつけて横たわっているぼくが相当可笑しいと言った表情だ。
「サイズ教えてよーサイズ」
今度は晴彦がそう席から言う。
一度放した手をぼくはアソコに戻そうとする。
オムツでも何でもいいから早く履かせて欲しかった。女の人の前でこの状態でいるのは死ぬ程恥ずかしい。
「もー、晴くんまで、やーねー」と、千香さんはいいながらもぼくの股間の長さを伝えるかのように、親指と人差し指で、「これくらいかな」とぼくのアソコのサイズを作った。意地悪なのか、親指と人差し指をくっつきそうなくらい寄せている。
「あわわ、ちっさーーーーー!!」と、晴彦。
大勢の人が笑った。顔がリンゴのように熱く、赤くなる。
笑いながら千香さんはぼくの両足を掴んで上に上げた。誰にも見られた事のないお尻の穴や玉の裏側が千香さんに向けられる。涙が出そうになる。
「よし、完成!」
オムツを完全に履かされると。ぼくは手を引いて立ち上がらされた。もちろん涎掛けにおしゃぶりをして、オムツの状態だ。
途端に客席からクスクス笑い声が聞こえる。
「本物の赤ちゃんみたいだね」と千香さんはそれだけ言って客席へ戻った。
「うん。確かに似合ってるな」
小石さんは真面目に頷く。
「それにしても、大きな赤ちゃんだな」と一言付け加える。ぼくの顔がまた赤くなる。
「よし、じゃあそれで演技をしてみようか」
もう頷くしかなかった。涙目になりながらぼくはさっきの演技をやらされた。
本物のオムツをして舞台を這い回るぼくは情けなくて仕方なかった。客席でもたまに押し殺したような笑い声が聞こえて、ぼくの羞恥心は高まった。
だぁ。だぁ。
「そこで泣いて。あ、もう涙目みたいだね。いやーキミ最高だよー!」
小石さんの嬉しそうな声が聞こえる。目に涙を浮かべながらぼくはもう一度声を上げた。
だぁ。だぁ。