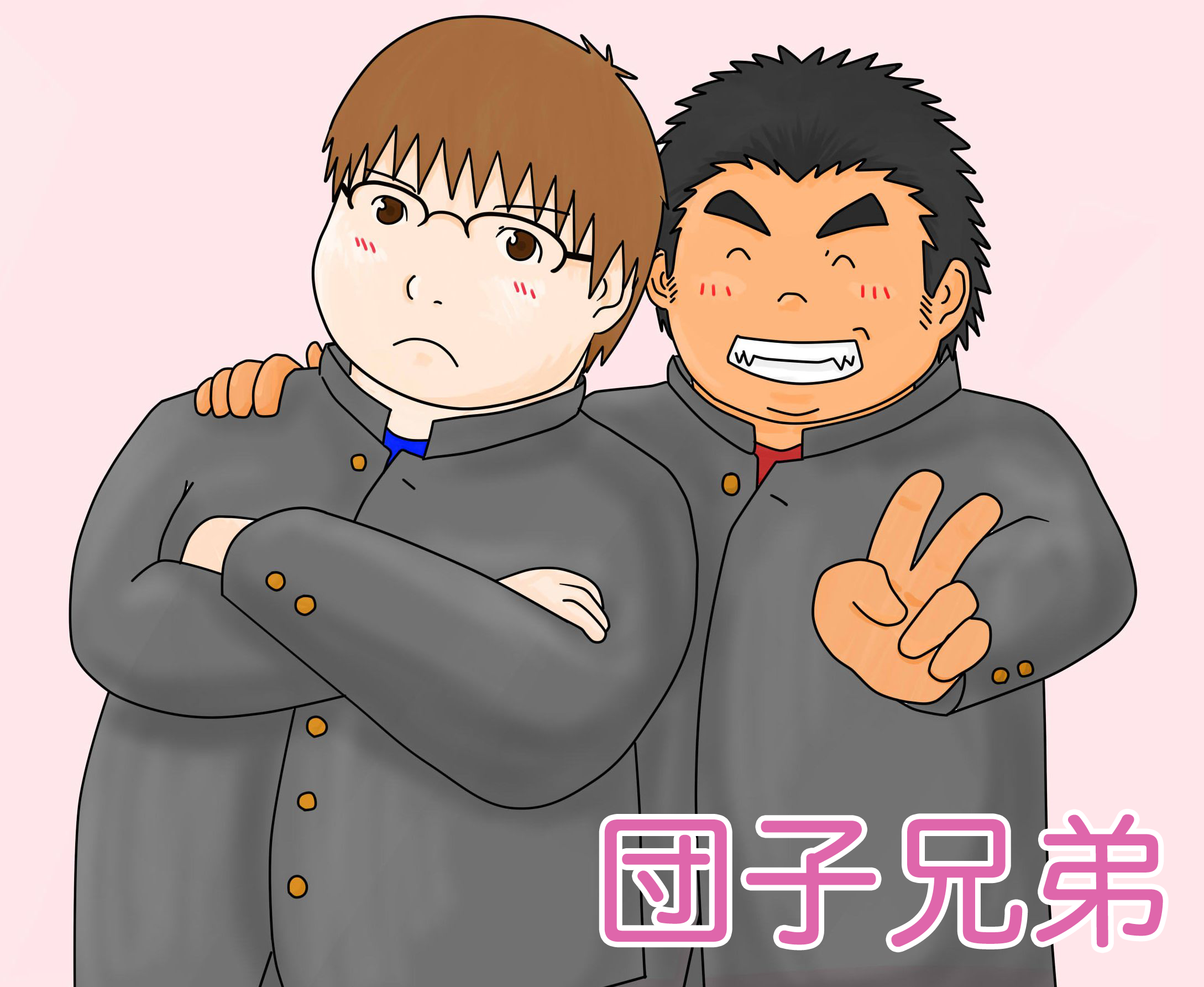太志くんの映画デブー
中学2年冬のことだった。ぼくは亀島中学に転校した。
同時にクラスからどっと笑い声がする。
家庭の事情でよく引っ越すのだけど、その度に毎回こうやって笑われた。
それもそのはず。転校生を期待していたクラスには豚みたいな体型のおデブが入ってきた
だけ。そりゃあ、みんな笑うに決まっている。
でも転校の多いぼくは、結構転校には慣れっこだった。
毎度やることなのだけど、学ランとその下のシャツをちょっとだけ捲ってへそを出して、ぼく膨れたお腹をみんなに見せつける。そして、タヌキのマネをしてお腹をポンポン両手で叩くのだ。これには敵対心も失せて、全員が大笑いすると言う訳だ。
「なんだよーあいつ」
「あははは、おもしれー」
ぼくも楽しくなってみんなが飽きるまで繰り返す。先生が、もういいからと言ってまたみんながどっと笑った。
「名前は、野本太志です。太いから、太志です」
またゲラゲラ生徒たちは笑う。先生ももうぼくのキャラをわかったのか大笑いだ。
デブは童顔だってよく言われるけど、自分で思うのもなんだが、ぼくもそうかもしれないなんてよく思ってしまう。
だって、よく小学生に間違えられたし。元々背も低いのもあるかもしれないが、地下鉄は子ども料金でも大丈夫だ。
その分、いろいろいじられるが、ぼくも楽しんで友達とじゃれ合う。どこに転校しても同じ楽しい毎日だった。
そして、その日の休み中。
ぼくはさっそく人気者だった。数人の男子生徒が笑顔でほっぺを軽くつねってきた。
「やめろよ〜」
ニコニコしながらぼくは手を払う。お腹や胸も触られた。
「デブ太志~」
「何百キロだよ~?」
なんて。
「触るな〜玩具じゃないぞー」
そう言って笑うぼくが面白いらしい。それでもすぐにみんなと仲良くできて、ぼくは安心して転校初日を終わらす事ができた。
帰り道、友達と帰ってからぼくはふーっとため息をついた。
寒いのに汗をかいていた。冷や汗だろう。さっと拭って、自分の部屋にこもった。
(ここが、一番落ち着く…)
ベッドで寝転がりながらぼくは今日のことを思い出した。途端に恥ずかしくなる。
そう、本当はぼくはもの凄く人見知りなのだ。幼稚園の頃なんて誰とも話さず、一人で砂場で遊んでいた子どもだった。
けれど家庭の事情でよく転校させられ、ぼくはある日このままじゃダメだと気づいた。
友達といっても毎回僅かな付き合いだ。人見知りだからといって、そんな短い付き合いを無駄にしちゃいけない。
そんな思いから生まれたぼくの行動は、人を笑わすこと。よくお笑い芸人などに自分と似た体型がいて、体を活かして人を笑わせているのをよく見かける。
さすがに芸人たちのように全裸にはなれないが、それでもお腹くらいなら見せれる。そう思ったのだ。
いわゆる腹芸なのだろう。ただ無論、自分の体に自信がある訳でもない。笑いを取る為にお腹を見せるなんて始めの頃はすごく緊張した。けれど、毎回クラスに恵まれてみんな笑ってくれ、ぼくはどんどん持ちネタを増やすことができたのだ。
持ちネタの一つに豚のマネというものがある。
今日は学校ではやらなかったが、これは結構ウケるのだ。
やり方は至って単純。豚のように四つん這いになって、女子生徒のお尻を追っかけ回すのだ。女子はスカートを押さえて悲鳴を上げて逃げ回り、男子はぼくや女子の姿を見て笑う。
やりすぎると後で、女子から本気で殴られるので注意が必要だ。
あとは赤ちゃんのマネ。床にお尻をついて足をバタバタさせ「だぁ、だぁ」と喚く。童顔のぼくならではの特技と言ったところか。
「太志ってプライドねーよな」
前の中学の友達にそう言われた。
「失礼な、メチャメチャあるぞ!!だぁ。だあ!!」
やりすぎると引き笑いをされるのでこれも注意が必要だ。
そんな訳で、ぼくはこのキャラクターを作ってからどこの学校へ行っても誰とでも仲良くできたのだ。
先生からも通知表に、「クラスを明るくしてくれる生徒」と書かれ、お母さんを安心させていた。
そして、それは。転校してから一週間程過ぎたある日のことだった。
帰る時間になりぼくはトイレに行って用をたしていると、同じクラスの席の近い晴彦という生徒がトイレに入ってきて、ぼくの隣の便器に立った。
「お前人気者だな」
「いや~それほどでも」
ぼくはへらへら笑う。晴彦は茶髪ヘアーで一見危なそうな雰囲気に見えて、まだ話したことがなかった。ぼくが豚のマネをして女子を追いかけているときも、たまにチラッと僕の方を見ながら、特に笑っている様子はなかったのである。
席が近いながら、いつ話せばいいのか自分も様子を伺っていた。
だが、不思議と晴彦は積極的にぼくに話しかけて来た。お陰でぼくはだんだんといつものように調子を取り戻すことができた。
「女子も言ってたぜ、結構かわいいって。お前小学生みたいだもんな。顔とかも」
「いや~人気者はつらいよ~」
ぼくは片方の手で大げさに頭をかくふりをした。今のは地味に嬉しかった。
(可愛い…やっぱりそうなんだ)
すると突然晴彦はぼくのものを覗き込もうとしてきた。
「あ…」
ぼくは腰を便器に押し付けて隠す。
「もしかして、おデブくん、君まだ生えてないんじゃないかい?」
下ねた系の冗談は苦手だったけど、ぼくは何とか頑張って対応した。
「あはは、まだまだ~ツールツル」
「へ〜」
晴彦が不気味に微笑んだ。
ぼくは、まだ振ってないアソコを引っ込める。
「あのさ」晴彦は徐に切り出した。
「俺さ、地域の映画サークルに入ってんだけど、主役いなくてな。…太志やんないか?」
「映画サークル…?」
突然の話にとまどう。
「幼いやつが、いいんだよね。主人公。お前ぴったしだからよ」
「主人公!!?ぼくが…!!?」
「そうそう」
「えー、でも。ぼく、演技無理だよ?」
主人公と言われ素直に喜んでしまったが、それでも改めて考える。前の学校で演技部とか言うのがあったが、大勢の前で堂々と演技をしている生徒たちはどんな気持ちで舞台に立っているのだろうかと不思議に思ったくらいだ。
うーん。とぼくは腕を組む。でも、主役か…。
悪くないと思った。みんなにちやほやされるのは嫌いじゃなかった。むしろ大好きだ。
けれど、やっぱり内心恥ずかしいのは隠せない。
答えを決めれないでいると、晴彦は「じゃあ、他の人に頼もうかな〜」と呟いた。
ん〜。また迷う。早く決めないと、おいしいところを他の生徒に持って行かれるかもしれない。
(よっし!!)
ぼくは腹をくくったようにポンッと手でなく、お腹をを叩いた。
「やってやろう!!」
「おお、そう言ってくれると嬉しいぜ。イケデブちゃん」
晴彦が微笑む。
「まぁぼくかっこいいから仕方ないよね~?」
ぼくは頭を掻いて晴彦に向かってそう言うと、晴彦はその答えに答えることなく、「じゃあ明日授業後誘うわ」とだけ言ってトイレを出て行った。
「オッケー」
ぼくはまた、ふざけてまたタヌキのまねをした。今度は誰も見ていなかった。
その日の夜は興奮して何だか寝付けなかった。明日のことを考えるとすごくどきどきして胸が高鳴るばかりだった。映画を撮ったらみんな見るんだろう。ヒーローものだったら主人公だから、女の子たちを助けて最後にほっぺにキスされたりして。んふふ。
一人でぼくは布団の中でニヤニヤ笑った。
そしたらもっと人気者になれて、すっごくちやほやされるんだろうな。
同時にクラスからどっと笑い声がする。
家庭の事情でよく引っ越すのだけど、その度に毎回こうやって笑われた。
それもそのはず。転校生を期待していたクラスには豚みたいな体型のおデブが入ってきた
だけ。そりゃあ、みんな笑うに決まっている。
でも転校の多いぼくは、結構転校には慣れっこだった。
毎度やることなのだけど、学ランとその下のシャツをちょっとだけ捲ってへそを出して、ぼく膨れたお腹をみんなに見せつける。そして、タヌキのマネをしてお腹をポンポン両手で叩くのだ。これには敵対心も失せて、全員が大笑いすると言う訳だ。
「なんだよーあいつ」
「あははは、おもしれー」
ぼくも楽しくなってみんなが飽きるまで繰り返す。先生が、もういいからと言ってまたみんながどっと笑った。
「名前は、野本太志です。太いから、太志です」
またゲラゲラ生徒たちは笑う。先生ももうぼくのキャラをわかったのか大笑いだ。
デブは童顔だってよく言われるけど、自分で思うのもなんだが、ぼくもそうかもしれないなんてよく思ってしまう。
だって、よく小学生に間違えられたし。元々背も低いのもあるかもしれないが、地下鉄は子ども料金でも大丈夫だ。
その分、いろいろいじられるが、ぼくも楽しんで友達とじゃれ合う。どこに転校しても同じ楽しい毎日だった。
そして、その日の休み中。
ぼくはさっそく人気者だった。数人の男子生徒が笑顔でほっぺを軽くつねってきた。
「やめろよ〜」
ニコニコしながらぼくは手を払う。お腹や胸も触られた。
「デブ太志~」
「何百キロだよ~?」
なんて。
「触るな〜玩具じゃないぞー」
そう言って笑うぼくが面白いらしい。それでもすぐにみんなと仲良くできて、ぼくは安心して転校初日を終わらす事ができた。
帰り道、友達と帰ってからぼくはふーっとため息をついた。
寒いのに汗をかいていた。冷や汗だろう。さっと拭って、自分の部屋にこもった。
(ここが、一番落ち着く…)
ベッドで寝転がりながらぼくは今日のことを思い出した。途端に恥ずかしくなる。
そう、本当はぼくはもの凄く人見知りなのだ。幼稚園の頃なんて誰とも話さず、一人で砂場で遊んでいた子どもだった。
けれど家庭の事情でよく転校させられ、ぼくはある日このままじゃダメだと気づいた。
友達といっても毎回僅かな付き合いだ。人見知りだからといって、そんな短い付き合いを無駄にしちゃいけない。
そんな思いから生まれたぼくの行動は、人を笑わすこと。よくお笑い芸人などに自分と似た体型がいて、体を活かして人を笑わせているのをよく見かける。
さすがに芸人たちのように全裸にはなれないが、それでもお腹くらいなら見せれる。そう思ったのだ。
いわゆる腹芸なのだろう。ただ無論、自分の体に自信がある訳でもない。笑いを取る為にお腹を見せるなんて始めの頃はすごく緊張した。けれど、毎回クラスに恵まれてみんな笑ってくれ、ぼくはどんどん持ちネタを増やすことができたのだ。
持ちネタの一つに豚のマネというものがある。
今日は学校ではやらなかったが、これは結構ウケるのだ。
やり方は至って単純。豚のように四つん這いになって、女子生徒のお尻を追っかけ回すのだ。女子はスカートを押さえて悲鳴を上げて逃げ回り、男子はぼくや女子の姿を見て笑う。
やりすぎると後で、女子から本気で殴られるので注意が必要だ。
あとは赤ちゃんのマネ。床にお尻をついて足をバタバタさせ「だぁ、だぁ」と喚く。童顔のぼくならではの特技と言ったところか。
「太志ってプライドねーよな」
前の中学の友達にそう言われた。
「失礼な、メチャメチャあるぞ!!だぁ。だあ!!」
やりすぎると引き笑いをされるのでこれも注意が必要だ。
そんな訳で、ぼくはこのキャラクターを作ってからどこの学校へ行っても誰とでも仲良くできたのだ。
先生からも通知表に、「クラスを明るくしてくれる生徒」と書かれ、お母さんを安心させていた。
そして、それは。転校してから一週間程過ぎたある日のことだった。
帰る時間になりぼくはトイレに行って用をたしていると、同じクラスの席の近い晴彦という生徒がトイレに入ってきて、ぼくの隣の便器に立った。
「お前人気者だな」
「いや~それほどでも」
ぼくはへらへら笑う。晴彦は茶髪ヘアーで一見危なそうな雰囲気に見えて、まだ話したことがなかった。ぼくが豚のマネをして女子を追いかけているときも、たまにチラッと僕の方を見ながら、特に笑っている様子はなかったのである。
席が近いながら、いつ話せばいいのか自分も様子を伺っていた。
だが、不思議と晴彦は積極的にぼくに話しかけて来た。お陰でぼくはだんだんといつものように調子を取り戻すことができた。
「女子も言ってたぜ、結構かわいいって。お前小学生みたいだもんな。顔とかも」
「いや~人気者はつらいよ~」
ぼくは片方の手で大げさに頭をかくふりをした。今のは地味に嬉しかった。
(可愛い…やっぱりそうなんだ)
すると突然晴彦はぼくのものを覗き込もうとしてきた。
「あ…」
ぼくは腰を便器に押し付けて隠す。
「もしかして、おデブくん、君まだ生えてないんじゃないかい?」
下ねた系の冗談は苦手だったけど、ぼくは何とか頑張って対応した。
「あはは、まだまだ~ツールツル」
「へ〜」
晴彦が不気味に微笑んだ。
ぼくは、まだ振ってないアソコを引っ込める。
「あのさ」晴彦は徐に切り出した。
「俺さ、地域の映画サークルに入ってんだけど、主役いなくてな。…太志やんないか?」
「映画サークル…?」
突然の話にとまどう。
「幼いやつが、いいんだよね。主人公。お前ぴったしだからよ」
「主人公!!?ぼくが…!!?」
「そうそう」
「えー、でも。ぼく、演技無理だよ?」
主人公と言われ素直に喜んでしまったが、それでも改めて考える。前の学校で演技部とか言うのがあったが、大勢の前で堂々と演技をしている生徒たちはどんな気持ちで舞台に立っているのだろうかと不思議に思ったくらいだ。
うーん。とぼくは腕を組む。でも、主役か…。
悪くないと思った。みんなにちやほやされるのは嫌いじゃなかった。むしろ大好きだ。
けれど、やっぱり内心恥ずかしいのは隠せない。
答えを決めれないでいると、晴彦は「じゃあ、他の人に頼もうかな〜」と呟いた。
ん〜。また迷う。早く決めないと、おいしいところを他の生徒に持って行かれるかもしれない。
(よっし!!)
ぼくは腹をくくったようにポンッと手でなく、お腹をを叩いた。
「やってやろう!!」
「おお、そう言ってくれると嬉しいぜ。イケデブちゃん」
晴彦が微笑む。
「まぁぼくかっこいいから仕方ないよね~?」
ぼくは頭を掻いて晴彦に向かってそう言うと、晴彦はその答えに答えることなく、「じゃあ明日授業後誘うわ」とだけ言ってトイレを出て行った。
「オッケー」
ぼくはまた、ふざけてまたタヌキのまねをした。今度は誰も見ていなかった。
その日の夜は興奮して何だか寝付けなかった。明日のことを考えるとすごくどきどきして胸が高鳴るばかりだった。映画を撮ったらみんな見るんだろう。ヒーローものだったら主人公だから、女の子たちを助けて最後にほっぺにキスされたりして。んふふ。
一人でぼくは布団の中でニヤニヤ笑った。
そしたらもっと人気者になれて、すっごくちやほやされるんだろうな。
テーマ : 同性愛、ホモ、レズ、バイセクシャル
ジャンル : アダルト
リコーダー少年
「よう、よう!!よくも俺の妹をやってくれたなぁ!」
俺は家の庭で、一人の少年に詰め寄った。まん丸の顔に肉付きのいい体格をしている。
そいつはいかにもいたずらっぽそうな元気っ子なデブ少年。だが、今は俺が怖くて弱気だ。
俺の後ろで、妹が俺を壁にして、デブに向かって舌を出す。
「ご……ごめんなさい」
小学6年の少年は震える声で謝った。名札には春樹と書いてある。
「何されたんだ?お前」
俺は妹にたずねる。
「靴隠された。そんでね、私のスカートめくってくんのよ。変態なのよ、こいつ」
弟が横目で春樹を睨みながら言う。春樹は顔を赤くした。
「そうかそうか」
俺は、その春樹の真ん丸い頭を手で掴んだ。
春樹は「ひっ!」と小さな悲鳴を上げる。
「どうしてやろうかなぁ。とりあえずお前も同じ目に合ってもらうかね」
俺は、さっとそいつの半ズボンを下げた。ピッチピチのブリーフが丸出しになる。
妹は嬉しそうに笑った。「春樹くん、パンツ丸出し~」
春樹は情けない格好で恥ずかしそうだ。
「ついでにパンツもいくか?デブ」
「イヤです……」春樹はさすがに必死に首を振る。
「え??聞こえない」
俺は笑いながら言った。
「私みたーい」妹が横で飛び跳ねた。
「けどなぁ~、さすがに、こいつも男だぜ。女のお前にちんこ見られたりしたら、もう一生笑いもんだぜ」
「えええー、いいじ~ん。お願い~お兄ちゃ~ん」
妹は甘えた声で笑った。春樹は顔を真っ青にした。
「そっかぁ~まぁ、お前が言うなら」
しぶしぶ、俺はデブ少年のパンツをずりさげた。
ポロンと太く短い、包茎と、玉が出る。
「見ぃいいちゃった!」
春樹はそれを手で隠す。女子にあれを見られるほど恥ずかしいことはないだろう。俺は思った。
「見られちゃったなぁ、お前」俺がにんまりと笑った。
「おい、足上げろ」
俺はそいつから短パンとパンツを取り上げた。靴も邪魔だったので一緒にひったくる。
そいつはシャツにフリチンでランドセルを背負いながら、恥ずかしそうに庭の真ん中で立っている。
妹が何度も春樹の手を何度も引っ張って股間からどけようとする
「やめろぉ、お、おい、やめろって!」
春樹は顔を真っ赤にする。
「普段威張ってるくせに」
「わかった!わかったから!よせって!お、お願い!!」
春樹は必死だ。
春樹は肩で息をしながら、既に汗だく。
「おい、お前」
俺は、春樹のランドセルに刺さったリコーダーを抜き取った。
「これ吹けるのか?」
「ええと・・・・」
「上手く拭けたら、ズボンはかしてやるよ」
俺は春樹にリコーダーを返した。春樹は片手で股間をガードしながら、それを持つ。
だが、片手では吹くことはできない。
「おいおい、真剣にやってんのか~?」
俺は、春樹を睨んだ。
「あ、あっ、すみません。」
春樹は慌ててそう言って、手を股間から放した。
またあの小さなものが・・・。妹が横で笑う。
「なんか適当な曲吹いてみろ」
俺が言った。春樹は学校で習ってる曲を、フリチンで吹き始める。
「違う違う~全然駄目」
俺は春樹からリコーダーを奪った。
「そんなんじゃ、パンツ履けねぇぞ」
俺は、リコーダーの先端を春樹のアソコに押し付けた。
グニュッと少年のあそこが曲がった。春樹が腰を引っ込める。
「やだぁ~汚い!」
妹が大声を出した。
「もう一度吹いてみろ。今度は上手くいくぜ」
春樹はリコーダーを握り締めながら、顔を真っ青にしていた。
涙目で春樹はリコーダーをそっと加える。
俺らは大笑いした。
少し吹いた時点で、俺はまたリコーダーを彼の短小にグリグリと擦り合わせる。
「ほら、もう一回」
俺は何度も同じことをやらせた。
春樹の柔らかいあそこも、徐々に硬いリコーダーの先端の刺激を受け、反応しつつあった。
俺はもう一度、春樹のあれからリコーダーを放し、そいつのアレを見た。
むくむくと大きくなってきている。
「あああああああ」妹が声を上げた。
「ボーーツキ、ボーツキぃい」
俺は春樹のリコーダーで硬く上を向いた、彼のあそこを叩いて弾かせる。
横に、縦に。ブルンブルンと春樹の勃起が揺れて、さらに硬さを増し、カキンと上を向く。
俺と妹がまた笑った。
「さぁ~~、そろそろ、ベスの餌の時間だなぁ。」
俺は立ち上がった。
「えーーーいいとこなのにぃ」
妹ががっかりして、口を尖らした。
俺は、チクワを冷蔵庫から出して、庭に持ってきた。
庭に大きな犬のベスがいる。
「ベス!!起きろ」
そして、隣後ろで必死に硬いアソコを隠そうとしているデブ。
俺は、ある作戦を実行した。
「これ、取ったらぶん殴るぞ」
俺は、春樹の勃起にちくわを丁寧に被せた。
春樹が驚いて声を詰まらす。
「あはは、すごい!!」
妹がベスに言う。「あれ食べて良いよ」
「あぁあ!!あわあああ」
俺はベスの鎖を解いた。
ベスが立ち上がり、春樹を追いかけた。
「ァあああああわあああああああわあああ!!」
春樹は必死で泣きながら逃げた。
勃起にちくわをはめながら庭中を駆け回る姿をいかにもみっともない。
俺らは横で爆笑だ。塀をよじ登ろうとして、でかいお尻が、こちらを向く。
ベスが馬鹿でないことは俺らは知っていた。ただのからかいだ。
「ほらほら~~早く走らないと。ちくわと一緒にちんこ喰われるぞ」
「女の子になっちゃうわよ~~」
俺らは横で冷やかす。
ベスはワンワン吼えながら、デブ少年の股間にはまったちくわを追った。
「いやだぁああああああ!!」
とうとう、ベスが春樹のちくわにぱくついた。
といっても、歯は立てていない。けれどデブ少年には相当ショックだったらしい。
ベスが彼のちんこからちくわを抜き取ったときには、春樹はへなへなと壁に与太れて、座ったかと思うと、既に元に戻った短小から、ジョロロロロとおしっこを垂れ流し始めた。
俺らは驚いてその様子を見ていると、春樹は少ししてシクシク泣き始めた。
俺は家の庭で、一人の少年に詰め寄った。まん丸の顔に肉付きのいい体格をしている。
そいつはいかにもいたずらっぽそうな元気っ子なデブ少年。だが、今は俺が怖くて弱気だ。
俺の後ろで、妹が俺を壁にして、デブに向かって舌を出す。
「ご……ごめんなさい」
小学6年の少年は震える声で謝った。名札には春樹と書いてある。
「何されたんだ?お前」
俺は妹にたずねる。
「靴隠された。そんでね、私のスカートめくってくんのよ。変態なのよ、こいつ」
弟が横目で春樹を睨みながら言う。春樹は顔を赤くした。
「そうかそうか」
俺は、その春樹の真ん丸い頭を手で掴んだ。
春樹は「ひっ!」と小さな悲鳴を上げる。
「どうしてやろうかなぁ。とりあえずお前も同じ目に合ってもらうかね」
俺は、さっとそいつの半ズボンを下げた。ピッチピチのブリーフが丸出しになる。
妹は嬉しそうに笑った。「春樹くん、パンツ丸出し~」
春樹は情けない格好で恥ずかしそうだ。
「ついでにパンツもいくか?デブ」
「イヤです……」春樹はさすがに必死に首を振る。
「え??聞こえない」
俺は笑いながら言った。
「私みたーい」妹が横で飛び跳ねた。
「けどなぁ~、さすがに、こいつも男だぜ。女のお前にちんこ見られたりしたら、もう一生笑いもんだぜ」
「えええー、いいじ~ん。お願い~お兄ちゃ~ん」
妹は甘えた声で笑った。春樹は顔を真っ青にした。
「そっかぁ~まぁ、お前が言うなら」
しぶしぶ、俺はデブ少年のパンツをずりさげた。
ポロンと太く短い、包茎と、玉が出る。
「見ぃいいちゃった!」
春樹はそれを手で隠す。女子にあれを見られるほど恥ずかしいことはないだろう。俺は思った。
「見られちゃったなぁ、お前」俺がにんまりと笑った。
「おい、足上げろ」
俺はそいつから短パンとパンツを取り上げた。靴も邪魔だったので一緒にひったくる。
そいつはシャツにフリチンでランドセルを背負いながら、恥ずかしそうに庭の真ん中で立っている。
妹が何度も春樹の手を何度も引っ張って股間からどけようとする
「やめろぉ、お、おい、やめろって!」
春樹は顔を真っ赤にする。
「普段威張ってるくせに」
「わかった!わかったから!よせって!お、お願い!!」
春樹は必死だ。
春樹は肩で息をしながら、既に汗だく。
「おい、お前」
俺は、春樹のランドセルに刺さったリコーダーを抜き取った。
「これ吹けるのか?」
「ええと・・・・」
「上手く拭けたら、ズボンはかしてやるよ」
俺は春樹にリコーダーを返した。春樹は片手で股間をガードしながら、それを持つ。
だが、片手では吹くことはできない。
「おいおい、真剣にやってんのか~?」
俺は、春樹を睨んだ。
「あ、あっ、すみません。」
春樹は慌ててそう言って、手を股間から放した。
またあの小さなものが・・・。妹が横で笑う。
「なんか適当な曲吹いてみろ」
俺が言った。春樹は学校で習ってる曲を、フリチンで吹き始める。
「違う違う~全然駄目」
俺は春樹からリコーダーを奪った。
「そんなんじゃ、パンツ履けねぇぞ」
俺は、リコーダーの先端を春樹のアソコに押し付けた。
グニュッと少年のあそこが曲がった。春樹が腰を引っ込める。
「やだぁ~汚い!」
妹が大声を出した。
「もう一度吹いてみろ。今度は上手くいくぜ」
春樹はリコーダーを握り締めながら、顔を真っ青にしていた。
涙目で春樹はリコーダーをそっと加える。
俺らは大笑いした。
少し吹いた時点で、俺はまたリコーダーを彼の短小にグリグリと擦り合わせる。
「ほら、もう一回」
俺は何度も同じことをやらせた。
春樹の柔らかいあそこも、徐々に硬いリコーダーの先端の刺激を受け、反応しつつあった。
俺はもう一度、春樹のあれからリコーダーを放し、そいつのアレを見た。
むくむくと大きくなってきている。
「あああああああ」妹が声を上げた。
「ボーーツキ、ボーツキぃい」
俺は春樹のリコーダーで硬く上を向いた、彼のあそこを叩いて弾かせる。
横に、縦に。ブルンブルンと春樹の勃起が揺れて、さらに硬さを増し、カキンと上を向く。
俺と妹がまた笑った。
「さぁ~~、そろそろ、ベスの餌の時間だなぁ。」
俺は立ち上がった。
「えーーーいいとこなのにぃ」
妹ががっかりして、口を尖らした。
俺は、チクワを冷蔵庫から出して、庭に持ってきた。
庭に大きな犬のベスがいる。
「ベス!!起きろ」
そして、隣後ろで必死に硬いアソコを隠そうとしているデブ。
俺は、ある作戦を実行した。
「これ、取ったらぶん殴るぞ」
俺は、春樹の勃起にちくわを丁寧に被せた。
春樹が驚いて声を詰まらす。
「あはは、すごい!!」
妹がベスに言う。「あれ食べて良いよ」
「あぁあ!!あわあああ」
俺はベスの鎖を解いた。
ベスが立ち上がり、春樹を追いかけた。
「ァあああああわあああああああわあああ!!」
春樹は必死で泣きながら逃げた。
勃起にちくわをはめながら庭中を駆け回る姿をいかにもみっともない。
俺らは横で爆笑だ。塀をよじ登ろうとして、でかいお尻が、こちらを向く。
ベスが馬鹿でないことは俺らは知っていた。ただのからかいだ。
「ほらほら~~早く走らないと。ちくわと一緒にちんこ喰われるぞ」
「女の子になっちゃうわよ~~」
俺らは横で冷やかす。
ベスはワンワン吼えながら、デブ少年の股間にはまったちくわを追った。
「いやだぁああああああ!!」
とうとう、ベスが春樹のちくわにぱくついた。
といっても、歯は立てていない。けれどデブ少年には相当ショックだったらしい。
ベスが彼のちんこからちくわを抜き取ったときには、春樹はへなへなと壁に与太れて、座ったかと思うと、既に元に戻った短小から、ジョロロロロとおしっこを垂れ流し始めた。
俺らは驚いてその様子を見ていると、春樹は少ししてシクシク泣き始めた。
赤ちゃん撮影
『知り合いでさ、プロの映画監督志望の人いるんだけど…お前、役者やってみる?』
「え?」
トイレで用を足し終えたところだった。大川耕太は顔を上げて隣の少年を見つめる。彼の名は晴彦と言った。あまり喋った事はなかったが、挨拶程度ならしたことはあるので、名前は知っていた。
「ぼくが?」
「ああ」
晴彦は素っ気なく頷いた。
「俺が紹介したんだ。学校で俳優になってみたいって言ってる子がいるってさ。連れて来てくれって」
彼の顔は大真面目だ。鳥肌が一気に立つのを感じた。そう。大川耕太は太っちょの体型に似合わず、生まれながらの俳優志望だったのだ。
「いいの?いいの?」
手も洗わずと子犬の様に晴彦へと飛びつく。
「うん。ただ、最初に審査あるけどな。そこで、通ればだぞ」
念を押したように彼は言った。「それでもやるか?」
「やるやる!」
嬉しくなってぼくはトイレの中ではしゃぎ回った。
それがぼくの人生を変えてしまうことも知らずに…。
その日。さっそくぼくは晴彦に着いてある場所へ向かった。
古びた施設のような所だった。自転車を止めて、晴彦とともに靴のまま中に入った。
「昨日眠れたか?」
「もちろん」
もちろん、眠れる訳がなかった。ずっと願って来た夢が今現実になりそうなのに…。ぼくは嬉しさで一晩中興奮して寝返りをうっていた。
「耕太、タフそうだからな」
「でしょ?」
「体型的にもな」
「まーね」
笑ったが、内心ちょっとムカッとする。体型の事は結構気にしていた。
階段を上がったところ直ぐ右に入り口があり、中に入った。ちょっと小さめのコンサート上の様なところだ。客席があり、舞台がある。
「すげー!」
「あそこで、演技するんだぜ?できる?」
「うん!楽しみ!」
胸の鼓動はますます高鳴った。
とりあえず、ぼくと晴彦は客席で座って待った。
「早く来すぎた?」
誰もいないホールを見渡しながらぼくが言うと、当たり前のように彼はこう言った。
「早く来た方がポイント高いだろ?」
「なるほどね」
時間があるうちにぼくは晴彦にいろいろな事を尋ねた。
妙に詳しい晴彦は、まず「おどおどしないこと」とぼくに忠告した。
それなら大丈夫かもしれない。常にぼくは自信家だ。そうでなければ、俳優になりたいなんて堂々と発表できるはずがない。
「あとは?」と訊くと、「それだけ」と言われた。
「演技のコツとか…いちお、初心者だし」
「別にそんなんいらねーよ。恥ずかしがらなきゃ初心者だって変わんないさ」
へー。と納得したように頷いた。一理あるかもしれない。大勢の前でどんな演技をさせられるのだろう。そしてやはり、最初の審査も演技のテストなのだろうか。
いろいろと疑問が浮かぶ。いつの間にか集合時間となり、大勢の人が中に入って来た。
「立って」と晴彦がぼくに言ってぼくは立ち上がる。
帽子を深く被り、ヒゲを生やしサングラスをかけたお兄さんが舞台に上がって指示をだしている。年は二十代くらいだろうか…、見た目からして監督だと分かった。
晴彦はぼくをその人の前まで連れて行ってくれた。舞台へ上がってぼくらは男の人の前に並んだ。
「ん?」
男は振り返った。
「小石さん、この子。前言ってたこですよ」
「へ〜」と、監督らしき男は、ぼくの体をじっくりと見つめる。
「面白いな。晴彦、本当にお前の言った通りだな」
少し薄ら笑いをした表情は気に障ったがぼくは元気よく自己紹介をして頭を下げた。
「耕太くんだね。元気そうで何より」
「はい!よろしくお願いします!」
またぼくは頭を深く下げる。
「へ〜」
ぼくの挨拶を聞いていた数人の大人の人が笑った。ちょっと恥ずかしくなってキョロキョロすると「おどおどするな」と晴彦に耳打ちされた。
「体重は?」
「40キロです!ってのは嘘で、60キロです」
体重の事で笑いを取りたくはなかったが、仕方がなかった。でもお陰で、ちょっとだけ周りが笑ってくれた。
「冗談も上手いなぁ。耕太くん、緊張とかしないの?」
「全然です」
脇の下の汗はびっしょりだ。
「んじゃ、最初はちょっと演技のテストしてもらおうかな」
小石さんはそう言ってぼくに一枚のプリントを差し出した。
「そこにテスト内容書いてあるから、目通して。テストは、3分後かな」
時計をちらっと見て舞台の方へとすぐに行ってしまう。ぼく席に戻って、はプリントを見つめた。
《赤ん坊の演技》
「え?」
トイレで用を足し終えたところだった。大川耕太は顔を上げて隣の少年を見つめる。彼の名は晴彦と言った。あまり喋った事はなかったが、挨拶程度ならしたことはあるので、名前は知っていた。
「ぼくが?」
「ああ」
晴彦は素っ気なく頷いた。
「俺が紹介したんだ。学校で俳優になってみたいって言ってる子がいるってさ。連れて来てくれって」
彼の顔は大真面目だ。鳥肌が一気に立つのを感じた。そう。大川耕太は太っちょの体型に似合わず、生まれながらの俳優志望だったのだ。
「いいの?いいの?」
手も洗わずと子犬の様に晴彦へと飛びつく。
「うん。ただ、最初に審査あるけどな。そこで、通ればだぞ」
念を押したように彼は言った。「それでもやるか?」
「やるやる!」
嬉しくなってぼくはトイレの中ではしゃぎ回った。
それがぼくの人生を変えてしまうことも知らずに…。
その日。さっそくぼくは晴彦に着いてある場所へ向かった。
古びた施設のような所だった。自転車を止めて、晴彦とともに靴のまま中に入った。
「昨日眠れたか?」
「もちろん」
もちろん、眠れる訳がなかった。ずっと願って来た夢が今現実になりそうなのに…。ぼくは嬉しさで一晩中興奮して寝返りをうっていた。
「耕太、タフそうだからな」
「でしょ?」
「体型的にもな」
「まーね」
笑ったが、内心ちょっとムカッとする。体型の事は結構気にしていた。
階段を上がったところ直ぐ右に入り口があり、中に入った。ちょっと小さめのコンサート上の様なところだ。客席があり、舞台がある。
「すげー!」
「あそこで、演技するんだぜ?できる?」
「うん!楽しみ!」
胸の鼓動はますます高鳴った。
とりあえず、ぼくと晴彦は客席で座って待った。
「早く来すぎた?」
誰もいないホールを見渡しながらぼくが言うと、当たり前のように彼はこう言った。
「早く来た方がポイント高いだろ?」
「なるほどね」
時間があるうちにぼくは晴彦にいろいろな事を尋ねた。
妙に詳しい晴彦は、まず「おどおどしないこと」とぼくに忠告した。
それなら大丈夫かもしれない。常にぼくは自信家だ。そうでなければ、俳優になりたいなんて堂々と発表できるはずがない。
「あとは?」と訊くと、「それだけ」と言われた。
「演技のコツとか…いちお、初心者だし」
「別にそんなんいらねーよ。恥ずかしがらなきゃ初心者だって変わんないさ」
へー。と納得したように頷いた。一理あるかもしれない。大勢の前でどんな演技をさせられるのだろう。そしてやはり、最初の審査も演技のテストなのだろうか。
いろいろと疑問が浮かぶ。いつの間にか集合時間となり、大勢の人が中に入って来た。
「立って」と晴彦がぼくに言ってぼくは立ち上がる。
帽子を深く被り、ヒゲを生やしサングラスをかけたお兄さんが舞台に上がって指示をだしている。年は二十代くらいだろうか…、見た目からして監督だと分かった。
晴彦はぼくをその人の前まで連れて行ってくれた。舞台へ上がってぼくらは男の人の前に並んだ。
「ん?」
男は振り返った。
「小石さん、この子。前言ってたこですよ」
「へ〜」と、監督らしき男は、ぼくの体をじっくりと見つめる。
「面白いな。晴彦、本当にお前の言った通りだな」
少し薄ら笑いをした表情は気に障ったがぼくは元気よく自己紹介をして頭を下げた。
「耕太くんだね。元気そうで何より」
「はい!よろしくお願いします!」
またぼくは頭を深く下げる。
「へ〜」
ぼくの挨拶を聞いていた数人の大人の人が笑った。ちょっと恥ずかしくなってキョロキョロすると「おどおどするな」と晴彦に耳打ちされた。
「体重は?」
「40キロです!ってのは嘘で、60キロです」
体重の事で笑いを取りたくはなかったが、仕方がなかった。でもお陰で、ちょっとだけ周りが笑ってくれた。
「冗談も上手いなぁ。耕太くん、緊張とかしないの?」
「全然です」
脇の下の汗はびっしょりだ。
「んじゃ、最初はちょっと演技のテストしてもらおうかな」
小石さんはそう言ってぼくに一枚のプリントを差し出した。
「そこにテスト内容書いてあるから、目通して。テストは、3分後かな」
時計をちらっと見て舞台の方へとすぐに行ってしまう。ぼく席に戻って、はプリントを見つめた。
《赤ん坊の演技》
萌えタイ
人より目立たなくてもいい。
つまらない人間だって言われても構わない。
僕はただ穏やかに生きていたいだけなんだ。
メタボ高校生のぼくは、ある日突然、ボクシングを始める事になったんだ。
今までに触れた事の無い世界へ飛び込むと同時にぼくが感じたのは、味わった事の無い充実感だった。
「ボクシングってこんなに面白いんだ」
始めてから一ヶ月、二ヶ月経っても全く体重の落ちないぼくだけれど、それでもボクシングは好き。大好き。これからもずっとやっていきたいって思う。
「バッカみたい」
…なんて可愛い顔して酷な事を言う妹の美香は、実はぼくにボクシングを始めるきっかけをくれた妹。
最近はぼくの姿を見てボクシングを始めたみたいだけど、ほんのちょっと心配。
それでも、ぼくはそんな妹に今でも感謝している。毎日ただボーッと生きているぼくに、『生きている』、『頑張れる』ってことを実感させてくれるスポーツを教えてくれたんだから。
それでも、妹がぼくにボクシングを教えるのは、あるキッカケがあったみたい。
だからこれは、ぼくの…じゃなくて。美香の物語って言った方がいいかもしれない。
美香がぼくにボクシングを与えるキッカケをくれる、それまでの物語。
亀山太一。ボクシング入会、1ヶ月前。
駅の近くを通れば、高校生がちらほら歩いているのが見えた。いつもの光景だ。ほとんど見慣れた制服の中に、たまに見たくない制服が混ざっている。
お兄ちゃんと一緒の高校の制服…。
別に、お兄ちゃんがいれば、遠くからでも分かるんだけれど。
お兄ちゃんに外で会いたくない
そんな風に思い始めたのは中学に上がり初めて間もない頃からだった。
「美香のお兄ちゃんって知ってる?超メタボなのよ」
ある友達の告白のせいで私はその時、社会から抹殺される様な気さえ感じた。
「言わないでよ、それ!」
本気で真っ青になった私に、それ以後友達同士で私の兄の話は永遠とタブーとされた。けれど、思春期の女友達同士だと、どうしても男の話になってしまうのは仕方が無い。
「ねーねー。誰かカッコいい男の子紹介してよー」
「美香いないのー?男友達とかさ。お兄さんとかでもいいんだけど」
「えぇっ?」
マクドナルドで手にしていたコーラを吹き出しそうになる。突然お兄ちゃんのデブ腹が頭に浮かんだからだ。
「え…?いるの!?美香のお兄ちゃん超見たい!」
「え。い、いや…いるにはいるけど…」
ガラにもなく言葉に詰まりながらも、咳き込んでるフリをしてハンカチで口を擦った。
「うちのはそういうのじゃ、ないから」
「何よ、意地悪〜。あーあ。私の弟のたっくんが、もう4歳上だったらなー」
「ルリの弟の達也くんだっけ?超可愛いもんね。来年中学入学でしょ?あたし予約しとこうかな」
「何言ってんの?今がちょうどいいでしょ?」
「やだ、春香ってショタコンだったー?」
兄の話題から外れた友達同士の話題にちょっとだけ私は苦笑いした。だが、また残酷な話題は振り出しに戻ってくる。
「でさ、美香のお兄ちゃん。今度紹介してよ。いいでしょ?あたしが美香の妹になるんだから、文句ないよね?」
「あのね、文句は無いけど…いや、それ以前に…ほんと、そういうのじゃ…」
地味に真剣な目を向けている茶髪の友達から私は遠慮がちに体勢を弾く。
「何よー。クラス1、美人で有名な亀山美香様の兄もどーせ、クラス1、イケメン王子なんでしょ。しかも、高校生…」
彼女もコーラをずずっと啜ると、はぁっとため息をついた。
「羨ましいなぁ」
本気でそう言っているように聞こえた。
「そうかな……」
私も苦笑いしながら、本気でそう呟いた。イケメンとはほど遠いだらしない体のお兄ちゃんを頭に浮かばせながら。
なんでうちのお兄ちゃんっこんなんなんだろう
「美香ー。ソースとって」
食事中、お父さんの横でコロッケを齧っているまん丸顔のお兄ちゃんを睨みつけながら私は今日の友達との会話を思い出していた。
「う…な、なんだよ…怖い顔して」
「別に」
私は小瓶を取ると乱暴にそれをお兄ちゃんに渡した。
「こ、これ…醤油なんだけど」
既にコロッケに醤油を浴びせてしまったお兄ちゃんは恨めしそうな目で私を見つめている。
「何よ。お兄ちゃんがボーッとしてるから悪いんでしょ?瓶なんて見ればわかるのに」
同じ形の小瓶に詰められた同じ色の醤油とソースは分かりやすい様にマークが付いている。どこの家庭でも同じ様なものだ。
「でもさ…このコロッケさ」
気弱なお兄ちゃんも食べ物となると少しは食いついてくる。けれど、絶対に不機嫌そうな私とは目を合わそうとしない。そういうへたれなところを見れば見る程、ムカついてくるんだ。2つも年が違うのに。情けない。
「何よ?文句あるの?」
低い声でそう言うと、いや別に、と小さな声でそう言ってお兄ちゃんは醤油味のコロッケをチビチビ食べ出した。お父さんが呆れた顔でお兄ちゃんと私を見比べたがすぐに新聞に目を戻した。いつもの事だ。お父さんもいちいち気にしていない。
部屋に入って、自分の布団で二度寝返りをうった。本棚の上に立てられた写真立てが目に入って、慌てて階段越しに叫ぶ。
「お母さん!また勝手に部屋に入った!?」
キッチンまで私の声は届かなかった。捨てることもできない家族写真を私は引き出しの奥に片付けて鍵をかけた。
写真には私と、真ん丸の体系のお兄ちゃんがとても仲良さそうに映っている。けれどそれは小さな頃の写真であって決して今ではない。
別に昔特別仲が良くて、そして今特別に仲が悪い訳ではないのだけど。けれど、どうしてもあの大きさとそして昔から変わらないヘタレなあの性格が、ド短気な私の神経を刺激するのだ。
美香は、反抗期よね。
それに比べて太一は、昔と変わらないんだから。
お兄ちゃんを褒めてるのか。それとも部屋に蓄えたお菓子を夕飯前に食ってばっかりのお兄ちゃんに飽きれて呟いたのか、またはそれとも、ただ何気なく呟いたのか、そんなお母さんの言葉は少しだけ私をムッとさせたことがある。
「それどういう意味よ」
「美香すぐ怒るもんな」
機嫌を悪くしていた私にさらにお兄ちゃんの無神経な言葉が追い打ちをかけて、お兄ちゃんのお尻を蹴って夕食を食べずに部屋に駆け上がった。
「お兄ちゃんに乱暴しちゃ駄目でしょ」
お母さんの声は聞こえたけれど、舌を出してドアを閉めた。
こんなお兄ちゃんいらない。
あんなんがお兄ちゃんなら必要ない。
どんなに嫌いでも、私たちの部屋は隣通し。同じ屋根の下で過ごす私はそんなお兄ちゃんを嫌でも毎日見なければならないのだ。
また寝返りをうって私は壁に鼻先をちょこんと付けた。木のいい匂いがした。それと同時にテレビの音が聞こえた。性格に言うとゲームのピコピコ音だ。
ああ、もう。
ちくしょー。
と、こういう時にしか言えない乱暴な口調でコントローラーをかちゃかちゃ動かしている。それを私にでも言ってみろよ。と、頭の中で呟いた。すると少しして声は止む。別に興味はないが、私は今度は壁に耳を当てる。負けたのか。どーせ、落ち込んでるのかな。
「ああああああああ!!くそおおおおお」
突然、お兄ちゃんの低い叫び声が聞こえた。私は声に驚いて体を引いた。ベッドから落ちそうになる。
「ゲームにしか文句言えないくせに」
顔が歪む。足で壁を思い切り蹴り飛ばした。私の怒りに答えるように声は聞こえなくなった。
その翌日。私は、駅前で声をかけられた。初めてのことじゃない。いつものことだけれど。顔が格好良かったので、友達同士だったけれど立ち止まって笑顔を作った。
「はは、可愛いね。笑顔も超タイプなんだけど。あ、俺ヨシキね。自己紹介早かったかな?」
今風の高校生のヨシキさんは、茶髪に長身でファッションセンスも抜群だった。スラットした手足も比べ物にならないくらいうちのお兄ちゃんとは違っている。
「美香ちゃんだっけ?メアド教えてよ」
ヨシキさんはそれだけ言って、手を振って笑って去っていった。
「いーなー美香!絶対当たりだよ!あの人!」
「どうすんの?連絡しちゃう?」
友人たちが横で騒ぐ。私は彼から受け取ったメアドの載った紙をもう一度見つめた。
少し考えてから、私は紙をたたんで、制服のポケットに突っ込んだ。
それからは、ヨシキさんとは学校帰りに会う生活が続いた。一緒にマクドナルドに行って同じメニューを注文した。今まで付き合った年上の男の人の中でもヨシキさんとは気も抜群に合った。
夜は寝る直前までメールをした。
『今日も遅くまでメールありがとう!明日も学校終わったら、いつものトコで会おうね(^o^)/』
『うん(^_^)また連絡する』
携帯を閉じてベッドに仰向けに倒れた。もうちょっとメールしたかったけれど自分からは言い出せない。しつこい女だと思われるのは嫌だった。どうせお風呂も入らないといけないし。
すると突然携帯が鳴って、私は飛び起きた。
ヨシキ。と、サブディスプレイに文字が浮かび上がっている。
「……はい」
私は呟くように返事した。
「ごめん。やっぱり、もうちょっと話ししたくて」
まるで運命のように思えた。ここまで気が合うなんて。胸をたからせながら私は携帯を握って、それから30分もヨシキさんと話していた。
電話を切ると私はパジャマを抱えて風呂場に向かった。お兄ちゃんの部屋からは何の音もなかったが何も気にせずに下の階へと向かう。洗面所に入るとシャワーの音が聞こえた。
「お母さん?うそ。私、今から入るんだけど。早く出てよー」
声はしない。今日は私が一番風呂だって約束したのに。信じられない。
「ねー、お母さん。もう!返事してよね。明日学校あるから、早く寝たいんだから」
思い切り浴槽の扉を開けた。そして私は体を凍り付かせた。見えたのは大きな背中とお尻だった。そう、ほかの誰でもないあのお兄ちゃんの。
悲鳴を上げると裸のお兄ちゃんは振り返って、ぎゃあああと、同じように声をあげる。さらに振り返った瞬間に世界で一番見たくないだらしのないお腹が目に飛び込んでくる。それより下も、見てしまったかもしれない。咄嗟に洗面所にあった石けんや空のボトルを投げつける。
「おわっ…や、ややめて、美香!しっ、閉めてよ!」
お兄ちゃんは慌てて洗面器で股間を隠しながら扉を閉めようとする。私だって閉めたい。けれど、これ以上あの物体に近づきたくない。
「来ないでよ!変態!最低!」
そう叫んで私はまた目を背けながら手探りさせる。だが、次に手に取ったのは運悪くもお兄ちゃんのどでかいトランクスだった。気を失いそうになりながらも悲鳴をあげてそれをお兄ちゃん目がけて投げつける。トランクスはうまく顔に被さり、さらにお兄ちゃんは石けんに躓いてひっくり返る。「あ、」と弱々しい声を上げたお兄ちゃんの股が開かれたかと思いきや、お兄ちゃんは腰を床へと叩き付けた。
「あ、お兄ちゃん、だ、大丈夫……」
思わず声をかけようとした私だったが、「いたたたたた」と腰をさするお兄ちゃんの股は全開に私の前で開かれていた。
「…ゲッ」
お兄ちゃんが気づいて股に手をおいたが時は既に遅かった。そう。その時見た光景は、私の人生の中で、一番卑劣な光景だっただろう。
もう声にならない音を喉からあげながら、私は部屋へと駆け上がって乱暴に扉を閉め、鍵をかけた。
もう二度とあの人と会話なんてしたくないと思った。
つまらない人間だって言われても構わない。
僕はただ穏やかに生きていたいだけなんだ。
メタボ高校生のぼくは、ある日突然、ボクシングを始める事になったんだ。
今までに触れた事の無い世界へ飛び込むと同時にぼくが感じたのは、味わった事の無い充実感だった。
「ボクシングってこんなに面白いんだ」
始めてから一ヶ月、二ヶ月経っても全く体重の落ちないぼくだけれど、それでもボクシングは好き。大好き。これからもずっとやっていきたいって思う。
「バッカみたい」
…なんて可愛い顔して酷な事を言う妹の美香は、実はぼくにボクシングを始めるきっかけをくれた妹。
最近はぼくの姿を見てボクシングを始めたみたいだけど、ほんのちょっと心配。
それでも、ぼくはそんな妹に今でも感謝している。毎日ただボーッと生きているぼくに、『生きている』、『頑張れる』ってことを実感させてくれるスポーツを教えてくれたんだから。
それでも、妹がぼくにボクシングを教えるのは、あるキッカケがあったみたい。
だからこれは、ぼくの…じゃなくて。美香の物語って言った方がいいかもしれない。
美香がぼくにボクシングを与えるキッカケをくれる、それまでの物語。
亀山太一。ボクシング入会、1ヶ月前。
駅の近くを通れば、高校生がちらほら歩いているのが見えた。いつもの光景だ。ほとんど見慣れた制服の中に、たまに見たくない制服が混ざっている。
お兄ちゃんと一緒の高校の制服…。
別に、お兄ちゃんがいれば、遠くからでも分かるんだけれど。
お兄ちゃんに外で会いたくない
そんな風に思い始めたのは中学に上がり初めて間もない頃からだった。
「美香のお兄ちゃんって知ってる?超メタボなのよ」
ある友達の告白のせいで私はその時、社会から抹殺される様な気さえ感じた。
「言わないでよ、それ!」
本気で真っ青になった私に、それ以後友達同士で私の兄の話は永遠とタブーとされた。けれど、思春期の女友達同士だと、どうしても男の話になってしまうのは仕方が無い。
「ねーねー。誰かカッコいい男の子紹介してよー」
「美香いないのー?男友達とかさ。お兄さんとかでもいいんだけど」
「えぇっ?」
マクドナルドで手にしていたコーラを吹き出しそうになる。突然お兄ちゃんのデブ腹が頭に浮かんだからだ。
「え…?いるの!?美香のお兄ちゃん超見たい!」
「え。い、いや…いるにはいるけど…」
ガラにもなく言葉に詰まりながらも、咳き込んでるフリをしてハンカチで口を擦った。
「うちのはそういうのじゃ、ないから」
「何よ、意地悪〜。あーあ。私の弟のたっくんが、もう4歳上だったらなー」
「ルリの弟の達也くんだっけ?超可愛いもんね。来年中学入学でしょ?あたし予約しとこうかな」
「何言ってんの?今がちょうどいいでしょ?」
「やだ、春香ってショタコンだったー?」
兄の話題から外れた友達同士の話題にちょっとだけ私は苦笑いした。だが、また残酷な話題は振り出しに戻ってくる。
「でさ、美香のお兄ちゃん。今度紹介してよ。いいでしょ?あたしが美香の妹になるんだから、文句ないよね?」
「あのね、文句は無いけど…いや、それ以前に…ほんと、そういうのじゃ…」
地味に真剣な目を向けている茶髪の友達から私は遠慮がちに体勢を弾く。
「何よー。クラス1、美人で有名な亀山美香様の兄もどーせ、クラス1、イケメン王子なんでしょ。しかも、高校生…」
彼女もコーラをずずっと啜ると、はぁっとため息をついた。
「羨ましいなぁ」
本気でそう言っているように聞こえた。
「そうかな……」
私も苦笑いしながら、本気でそう呟いた。イケメンとはほど遠いだらしない体のお兄ちゃんを頭に浮かばせながら。
なんでうちのお兄ちゃんっこんなんなんだろう
「美香ー。ソースとって」
食事中、お父さんの横でコロッケを齧っているまん丸顔のお兄ちゃんを睨みつけながら私は今日の友達との会話を思い出していた。
「う…な、なんだよ…怖い顔して」
「別に」
私は小瓶を取ると乱暴にそれをお兄ちゃんに渡した。
「こ、これ…醤油なんだけど」
既にコロッケに醤油を浴びせてしまったお兄ちゃんは恨めしそうな目で私を見つめている。
「何よ。お兄ちゃんがボーッとしてるから悪いんでしょ?瓶なんて見ればわかるのに」
同じ形の小瓶に詰められた同じ色の醤油とソースは分かりやすい様にマークが付いている。どこの家庭でも同じ様なものだ。
「でもさ…このコロッケさ」
気弱なお兄ちゃんも食べ物となると少しは食いついてくる。けれど、絶対に不機嫌そうな私とは目を合わそうとしない。そういうへたれなところを見れば見る程、ムカついてくるんだ。2つも年が違うのに。情けない。
「何よ?文句あるの?」
低い声でそう言うと、いや別に、と小さな声でそう言ってお兄ちゃんは醤油味のコロッケをチビチビ食べ出した。お父さんが呆れた顔でお兄ちゃんと私を見比べたがすぐに新聞に目を戻した。いつもの事だ。お父さんもいちいち気にしていない。
部屋に入って、自分の布団で二度寝返りをうった。本棚の上に立てられた写真立てが目に入って、慌てて階段越しに叫ぶ。
「お母さん!また勝手に部屋に入った!?」
キッチンまで私の声は届かなかった。捨てることもできない家族写真を私は引き出しの奥に片付けて鍵をかけた。
写真には私と、真ん丸の体系のお兄ちゃんがとても仲良さそうに映っている。けれどそれは小さな頃の写真であって決して今ではない。
別に昔特別仲が良くて、そして今特別に仲が悪い訳ではないのだけど。けれど、どうしてもあの大きさとそして昔から変わらないヘタレなあの性格が、ド短気な私の神経を刺激するのだ。
美香は、反抗期よね。
それに比べて太一は、昔と変わらないんだから。
お兄ちゃんを褒めてるのか。それとも部屋に蓄えたお菓子を夕飯前に食ってばっかりのお兄ちゃんに飽きれて呟いたのか、またはそれとも、ただ何気なく呟いたのか、そんなお母さんの言葉は少しだけ私をムッとさせたことがある。
「それどういう意味よ」
「美香すぐ怒るもんな」
機嫌を悪くしていた私にさらにお兄ちゃんの無神経な言葉が追い打ちをかけて、お兄ちゃんのお尻を蹴って夕食を食べずに部屋に駆け上がった。
「お兄ちゃんに乱暴しちゃ駄目でしょ」
お母さんの声は聞こえたけれど、舌を出してドアを閉めた。
こんなお兄ちゃんいらない。
あんなんがお兄ちゃんなら必要ない。
どんなに嫌いでも、私たちの部屋は隣通し。同じ屋根の下で過ごす私はそんなお兄ちゃんを嫌でも毎日見なければならないのだ。
また寝返りをうって私は壁に鼻先をちょこんと付けた。木のいい匂いがした。それと同時にテレビの音が聞こえた。性格に言うとゲームのピコピコ音だ。
ああ、もう。
ちくしょー。
と、こういう時にしか言えない乱暴な口調でコントローラーをかちゃかちゃ動かしている。それを私にでも言ってみろよ。と、頭の中で呟いた。すると少しして声は止む。別に興味はないが、私は今度は壁に耳を当てる。負けたのか。どーせ、落ち込んでるのかな。
「ああああああああ!!くそおおおおお」
突然、お兄ちゃんの低い叫び声が聞こえた。私は声に驚いて体を引いた。ベッドから落ちそうになる。
「ゲームにしか文句言えないくせに」
顔が歪む。足で壁を思い切り蹴り飛ばした。私の怒りに答えるように声は聞こえなくなった。
その翌日。私は、駅前で声をかけられた。初めてのことじゃない。いつものことだけれど。顔が格好良かったので、友達同士だったけれど立ち止まって笑顔を作った。
「はは、可愛いね。笑顔も超タイプなんだけど。あ、俺ヨシキね。自己紹介早かったかな?」
今風の高校生のヨシキさんは、茶髪に長身でファッションセンスも抜群だった。スラットした手足も比べ物にならないくらいうちのお兄ちゃんとは違っている。
「美香ちゃんだっけ?メアド教えてよ」
ヨシキさんはそれだけ言って、手を振って笑って去っていった。
「いーなー美香!絶対当たりだよ!あの人!」
「どうすんの?連絡しちゃう?」
友人たちが横で騒ぐ。私は彼から受け取ったメアドの載った紙をもう一度見つめた。
少し考えてから、私は紙をたたんで、制服のポケットに突っ込んだ。
それからは、ヨシキさんとは学校帰りに会う生活が続いた。一緒にマクドナルドに行って同じメニューを注文した。今まで付き合った年上の男の人の中でもヨシキさんとは気も抜群に合った。
夜は寝る直前までメールをした。
『今日も遅くまでメールありがとう!明日も学校終わったら、いつものトコで会おうね(^o^)/』
『うん(^_^)また連絡する』
携帯を閉じてベッドに仰向けに倒れた。もうちょっとメールしたかったけれど自分からは言い出せない。しつこい女だと思われるのは嫌だった。どうせお風呂も入らないといけないし。
すると突然携帯が鳴って、私は飛び起きた。
ヨシキ。と、サブディスプレイに文字が浮かび上がっている。
「……はい」
私は呟くように返事した。
「ごめん。やっぱり、もうちょっと話ししたくて」
まるで運命のように思えた。ここまで気が合うなんて。胸をたからせながら私は携帯を握って、それから30分もヨシキさんと話していた。
電話を切ると私はパジャマを抱えて風呂場に向かった。お兄ちゃんの部屋からは何の音もなかったが何も気にせずに下の階へと向かう。洗面所に入るとシャワーの音が聞こえた。
「お母さん?うそ。私、今から入るんだけど。早く出てよー」
声はしない。今日は私が一番風呂だって約束したのに。信じられない。
「ねー、お母さん。もう!返事してよね。明日学校あるから、早く寝たいんだから」
思い切り浴槽の扉を開けた。そして私は体を凍り付かせた。見えたのは大きな背中とお尻だった。そう、ほかの誰でもないあのお兄ちゃんの。
悲鳴を上げると裸のお兄ちゃんは振り返って、ぎゃあああと、同じように声をあげる。さらに振り返った瞬間に世界で一番見たくないだらしのないお腹が目に飛び込んでくる。それより下も、見てしまったかもしれない。咄嗟に洗面所にあった石けんや空のボトルを投げつける。
「おわっ…や、ややめて、美香!しっ、閉めてよ!」
お兄ちゃんは慌てて洗面器で股間を隠しながら扉を閉めようとする。私だって閉めたい。けれど、これ以上あの物体に近づきたくない。
「来ないでよ!変態!最低!」
そう叫んで私はまた目を背けながら手探りさせる。だが、次に手に取ったのは運悪くもお兄ちゃんのどでかいトランクスだった。気を失いそうになりながらも悲鳴をあげてそれをお兄ちゃん目がけて投げつける。トランクスはうまく顔に被さり、さらにお兄ちゃんは石けんに躓いてひっくり返る。「あ、」と弱々しい声を上げたお兄ちゃんの股が開かれたかと思いきや、お兄ちゃんは腰を床へと叩き付けた。
「あ、お兄ちゃん、だ、大丈夫……」
思わず声をかけようとした私だったが、「いたたたたた」と腰をさするお兄ちゃんの股は全開に私の前で開かれていた。
「…ゲッ」
お兄ちゃんが気づいて股に手をおいたが時は既に遅かった。そう。その時見た光景は、私の人生の中で、一番卑劣な光景だっただろう。
もう声にならない音を喉からあげながら、私は部屋へと駆け上がって乱暴に扉を閉め、鍵をかけた。
もう二度とあの人と会話なんてしたくないと思った。
ケータイ
学校に携帯電話を持ち込み禁止とする。そんな規則を緩和させたのは生徒会だった。元より全学年生徒対象のアンケートのほとんどの回答が携帯電話についての不満だった。隣に位置する猛符中学では携帯電話を授業中使用していても怒られないという噂が校内に広がったことからも、教師は生徒の意見から目を逸らすことができなかった。生徒会会長が教師に携帯電話の持ち込み許可を提案し、ついにそれが先週の教師の会議で議決された。
携帯電話持ち込み可という新しい学校制度に誰もが心を躍らせたが、小型電化製品に慣れない少年は少なからずいた。携帯をまだ買ってもらっていない少年だ。
巧海の家は貧乏というわけではなかった。ごく一般的な家庭で、人と同じような物を食べて育った。でなければ、彼の体は人よりも肥えていないだろうし。プールで浮き輪につっかえる心配もなかったはずだ。
巧海は生まれつきデブだった。肥えていた。ふくよかな腹を持って生まれた少年だった。幼く澄んだ目つきは周囲の人々を魅了させた。しかし彼の母親には巧海のそんな甘えた視線は全くと言っていいほど通用しなかった。
「高校に入ってからでいいでしょ」
「クラスのみんな持ってるし」
「みんなはみんな。うちはうち。何度言っても無駄。買いません」
結局何度頼んでも携帯を買ってもらえず、巧海は学校で友人同士が携帯を触っているのを恨めしそうに眺めていた。
その日は、雨だった。湿った空気に肌が触れるのが嫌で、数学の授業が鬱陶しく思えた。いつもより長く感じる。授業が終わると、わっと生徒達は席を立ったが誰も外には出ようとしない。廊下にさえも。
携帯を広げて、騒ぎ出す。巧海のように買ってもらっていない生徒もいたが、彼らは小型電子機器をいじる生徒の周りに集まって塊を作る。
「何かしようよ」
いつまでも携帯を眺めている友人に耐えきれず巧海は声を掛けた。彼も巧海と同じく携帯持っていない組である。
「遊ぼって」
熱心に小型画面に食い入るその友人の横顔に巧海は苛立ちを感じた。何が携帯だよ、と思った。ただの玩具じゃんか。どこが面白いんだよ。ぼそりと呟く。負け惜しみのつもりだった。そしてもちろん普段なら絶対に人前では言えない皮肉だった。全員の視線はあっという間に、巧海へと注がれた。
運が悪かったとしか思えなかった。その日。携帯の新機種を手に入れた生徒、瑠斗は買ったばかりの携帯を学校に持ち込んだことから、彼を囲んだ男子生徒からは偶然にも異様な盛り上がりをみせていた。誰もが新機種の携帯のデザインと機能の虜になり、熱心に新機種を買ったばかりの瑠斗の自慢の入り交じったトークに耳を傾けていたのだ。
そこへ入っていったのが惚けたような顔をした巧海だ。携帯の何がわかるんだよ、と他生徒が口々に巧海を非難した。「持ってないからって、僻むなよ」そんな声も飛ぶ。
「いや、別に。そんなつもりじゃ…」
元々気弱な巧海は人の携帯に文句を付けるつもりはなかった。ましてやクラスでもリーダー格の瑠斗に対してなら尚更だ。
「ただの玩具なんだってさ。そんな玩具も持ってないんじゃん、お前。携帯の使い方なんて知らないだろ」
知っていた。姉の携帯電話なら隠れて触ったことがある。基本的な操作知識程度なら巧海も持っていた。しかしいつの間にか、うんとも言えない状況になってきているのに巧海は気がついた。雨のせいだろうか。じめりと湿り気のある空気。些細なことでこみ上げて来る苛立ちを抱えているのは、自分だけでないと気づく。
「そう言えばさー。瑠斗くんの携帯ってカメラ機能良かったことない?」一人の少年が偶然言った。
「そうそう、それ目当てで買ったんだよな。千二百万画素。超綺麗だよ」
ピピッと電子音が響いて、巧海は目をぱちくりとさせた。瑠斗の持っている携帯のカメラが自分に向いている。顔を背けたが大分遅かった。
「うわあ。豚顔だ」瑠斗がニヤニヤしながら笑って、画面に映し出された巧海の表情を周りに見せる。ぽかーんと口を開いた巧海の表情は彼らが共に言う「間抜け面」にぴったりと当てはまっている。
「やめてよ」
「やめないよ?」
言葉通りに彼はまたカメラの音を鳴らした。偶然巧海がカメラを意識して背を向けたため、今度は画面に巧海の尻が映ってしまう。どっと生徒達が笑う。
「でっけぇー」
「豚尻じゃん。豚尻」
「見せて見せて。うわーきんもー!」
制服の上からでも下半身のお尻の部分だけ撮られたことは巧海にとって莫大な屈辱だった。「消してよ」と、携帯を片手にケラケラ笑っている瑠斗に食いつく。
「もう保存しちゃったもんねー」
子どものような声をあげて、少年は巧海を煽った。
「いいから、消して。お願い」
「しつこいデブだな!」
割と大人しめの性格の巧海がしつこく瑠斗に歩み寄ったためもあり、瑠斗は怒り任せに彼の腹をシューズで蹴飛ばした。
バランスを崩した巧海は背中から後ろに倒れ、床に尻餅をつく。反動で近くの椅子が横向きに倒れ、大きな物音が教室に響いた。クラス中の視線が巧海、そして瑠斗へと注がれる。シンと静まりかえった教室の真ん中で、巧海は瞼に僅かに涙を浮かべていた。
「あいつ、先生に言うんじゃね?」
昼休みの時間になった時のこと。携帯のゲームを遊んでいる瑠斗にメガネを掛けた少年がそう声を掛けた。
「それくらいで言うか?ふつー」
「あり得るって、あいつ。妙に真面目だもん」
隣の生徒の声がまたする。ああ、死んだ。画面にGAMEOVERと赤い文字が浮き出る。携帯を徐に閉じ、そうだな、と瑠斗は呟く。
「でも、やばくね?先生に言われたら携帯持ち込み禁止になるぞ」
「でも生徒会で決まったことだろ?」
「クラス単位でならあると思うぜ。授業中にメールやってた三年のクラス。もう禁止になったらしい」
まだ携帯を持ち込み可になってから二週間も経っていない。だとしたらどれだけ悲惨だろう。瑠斗は心の中でそんなことを考えた。やっと待ち望み、自分たちの手で変えた規則だ。今更携帯を持ち込み不可にされるのなんて真っ平だ。常日日頃から携帯電話を握りしめている瑠斗自身、多数の生徒に持ち込みを許可にするように呼びかけたのは事実だった。実際、数十票ほど不正も働いた。バレていないと思う。
「じゃあ、あいつがチクったら禁止ってこと?」
「それ、ウザいな。んじゃ、先生に言わないように言っておくか」
「聞かないだろあの豚。やるなら、もっと脅迫めいたことで口止めしないと」
瑠斗の隣の椅子に座っている男子生徒が思いついたようにそう言った。
「どうやって?」
「さっきの巧海の尻。ばらまくとか」
「あんなん誰かわかんねーよ」
「あいつの豚顔もあるじゃん」
「そんだけで口止めになるかー?」
適当に思いついた案を数人の生徒で出し合い、ふざけたように笑い合う。本気で言っているようで、誰一人として本気にはならない。誰もが暇つぶしの雑談のように思っていた。しかしいつの間にか、提案の中身は徐々に過激な物へと形を変えていく。
それだったら口止めにはなるだろ。いや、無理だろそれ。でもやってみたら、面白くないか?バレたらまずいって。口止め用にやるんだろ、だから大丈夫だって。
————やっちまおうぜ
携帯電話持ち込み可という新しい学校制度に誰もが心を躍らせたが、小型電化製品に慣れない少年は少なからずいた。携帯をまだ買ってもらっていない少年だ。
巧海の家は貧乏というわけではなかった。ごく一般的な家庭で、人と同じような物を食べて育った。でなければ、彼の体は人よりも肥えていないだろうし。プールで浮き輪につっかえる心配もなかったはずだ。
巧海は生まれつきデブだった。肥えていた。ふくよかな腹を持って生まれた少年だった。幼く澄んだ目つきは周囲の人々を魅了させた。しかし彼の母親には巧海のそんな甘えた視線は全くと言っていいほど通用しなかった。
「高校に入ってからでいいでしょ」
「クラスのみんな持ってるし」
「みんなはみんな。うちはうち。何度言っても無駄。買いません」
結局何度頼んでも携帯を買ってもらえず、巧海は学校で友人同士が携帯を触っているのを恨めしそうに眺めていた。
その日は、雨だった。湿った空気に肌が触れるのが嫌で、数学の授業が鬱陶しく思えた。いつもより長く感じる。授業が終わると、わっと生徒達は席を立ったが誰も外には出ようとしない。廊下にさえも。
携帯を広げて、騒ぎ出す。巧海のように買ってもらっていない生徒もいたが、彼らは小型電子機器をいじる生徒の周りに集まって塊を作る。
「何かしようよ」
いつまでも携帯を眺めている友人に耐えきれず巧海は声を掛けた。彼も巧海と同じく携帯持っていない組である。
「遊ぼって」
熱心に小型画面に食い入るその友人の横顔に巧海は苛立ちを感じた。何が携帯だよ、と思った。ただの玩具じゃんか。どこが面白いんだよ。ぼそりと呟く。負け惜しみのつもりだった。そしてもちろん普段なら絶対に人前では言えない皮肉だった。全員の視線はあっという間に、巧海へと注がれた。
運が悪かったとしか思えなかった。その日。携帯の新機種を手に入れた生徒、瑠斗は買ったばかりの携帯を学校に持ち込んだことから、彼を囲んだ男子生徒からは偶然にも異様な盛り上がりをみせていた。誰もが新機種の携帯のデザインと機能の虜になり、熱心に新機種を買ったばかりの瑠斗の自慢の入り交じったトークに耳を傾けていたのだ。
そこへ入っていったのが惚けたような顔をした巧海だ。携帯の何がわかるんだよ、と他生徒が口々に巧海を非難した。「持ってないからって、僻むなよ」そんな声も飛ぶ。
「いや、別に。そんなつもりじゃ…」
元々気弱な巧海は人の携帯に文句を付けるつもりはなかった。ましてやクラスでもリーダー格の瑠斗に対してなら尚更だ。
「ただの玩具なんだってさ。そんな玩具も持ってないんじゃん、お前。携帯の使い方なんて知らないだろ」
知っていた。姉の携帯電話なら隠れて触ったことがある。基本的な操作知識程度なら巧海も持っていた。しかしいつの間にか、うんとも言えない状況になってきているのに巧海は気がついた。雨のせいだろうか。じめりと湿り気のある空気。些細なことでこみ上げて来る苛立ちを抱えているのは、自分だけでないと気づく。
「そう言えばさー。瑠斗くんの携帯ってカメラ機能良かったことない?」一人の少年が偶然言った。
「そうそう、それ目当てで買ったんだよな。千二百万画素。超綺麗だよ」
ピピッと電子音が響いて、巧海は目をぱちくりとさせた。瑠斗の持っている携帯のカメラが自分に向いている。顔を背けたが大分遅かった。
「うわあ。豚顔だ」瑠斗がニヤニヤしながら笑って、画面に映し出された巧海の表情を周りに見せる。ぽかーんと口を開いた巧海の表情は彼らが共に言う「間抜け面」にぴったりと当てはまっている。
「やめてよ」
「やめないよ?」
言葉通りに彼はまたカメラの音を鳴らした。偶然巧海がカメラを意識して背を向けたため、今度は画面に巧海の尻が映ってしまう。どっと生徒達が笑う。
「でっけぇー」
「豚尻じゃん。豚尻」
「見せて見せて。うわーきんもー!」
制服の上からでも下半身のお尻の部分だけ撮られたことは巧海にとって莫大な屈辱だった。「消してよ」と、携帯を片手にケラケラ笑っている瑠斗に食いつく。
「もう保存しちゃったもんねー」
子どものような声をあげて、少年は巧海を煽った。
「いいから、消して。お願い」
「しつこいデブだな!」
割と大人しめの性格の巧海がしつこく瑠斗に歩み寄ったためもあり、瑠斗は怒り任せに彼の腹をシューズで蹴飛ばした。
バランスを崩した巧海は背中から後ろに倒れ、床に尻餅をつく。反動で近くの椅子が横向きに倒れ、大きな物音が教室に響いた。クラス中の視線が巧海、そして瑠斗へと注がれる。シンと静まりかえった教室の真ん中で、巧海は瞼に僅かに涙を浮かべていた。
「あいつ、先生に言うんじゃね?」
昼休みの時間になった時のこと。携帯のゲームを遊んでいる瑠斗にメガネを掛けた少年がそう声を掛けた。
「それくらいで言うか?ふつー」
「あり得るって、あいつ。妙に真面目だもん」
隣の生徒の声がまたする。ああ、死んだ。画面にGAMEOVERと赤い文字が浮き出る。携帯を徐に閉じ、そうだな、と瑠斗は呟く。
「でも、やばくね?先生に言われたら携帯持ち込み禁止になるぞ」
「でも生徒会で決まったことだろ?」
「クラス単位でならあると思うぜ。授業中にメールやってた三年のクラス。もう禁止になったらしい」
まだ携帯を持ち込み可になってから二週間も経っていない。だとしたらどれだけ悲惨だろう。瑠斗は心の中でそんなことを考えた。やっと待ち望み、自分たちの手で変えた規則だ。今更携帯を持ち込み不可にされるのなんて真っ平だ。常日日頃から携帯電話を握りしめている瑠斗自身、多数の生徒に持ち込みを許可にするように呼びかけたのは事実だった。実際、数十票ほど不正も働いた。バレていないと思う。
「じゃあ、あいつがチクったら禁止ってこと?」
「それ、ウザいな。んじゃ、先生に言わないように言っておくか」
「聞かないだろあの豚。やるなら、もっと脅迫めいたことで口止めしないと」
瑠斗の隣の椅子に座っている男子生徒が思いついたようにそう言った。
「どうやって?」
「さっきの巧海の尻。ばらまくとか」
「あんなん誰かわかんねーよ」
「あいつの豚顔もあるじゃん」
「そんだけで口止めになるかー?」
適当に思いついた案を数人の生徒で出し合い、ふざけたように笑い合う。本気で言っているようで、誰一人として本気にはならない。誰もが暇つぶしの雑談のように思っていた。しかしいつの間にか、提案の中身は徐々に過激な物へと形を変えていく。
それだったら口止めにはなるだろ。いや、無理だろそれ。でもやってみたら、面白くないか?バレたらまずいって。口止め用にやるんだろ、だから大丈夫だって。
————やっちまおうぜ