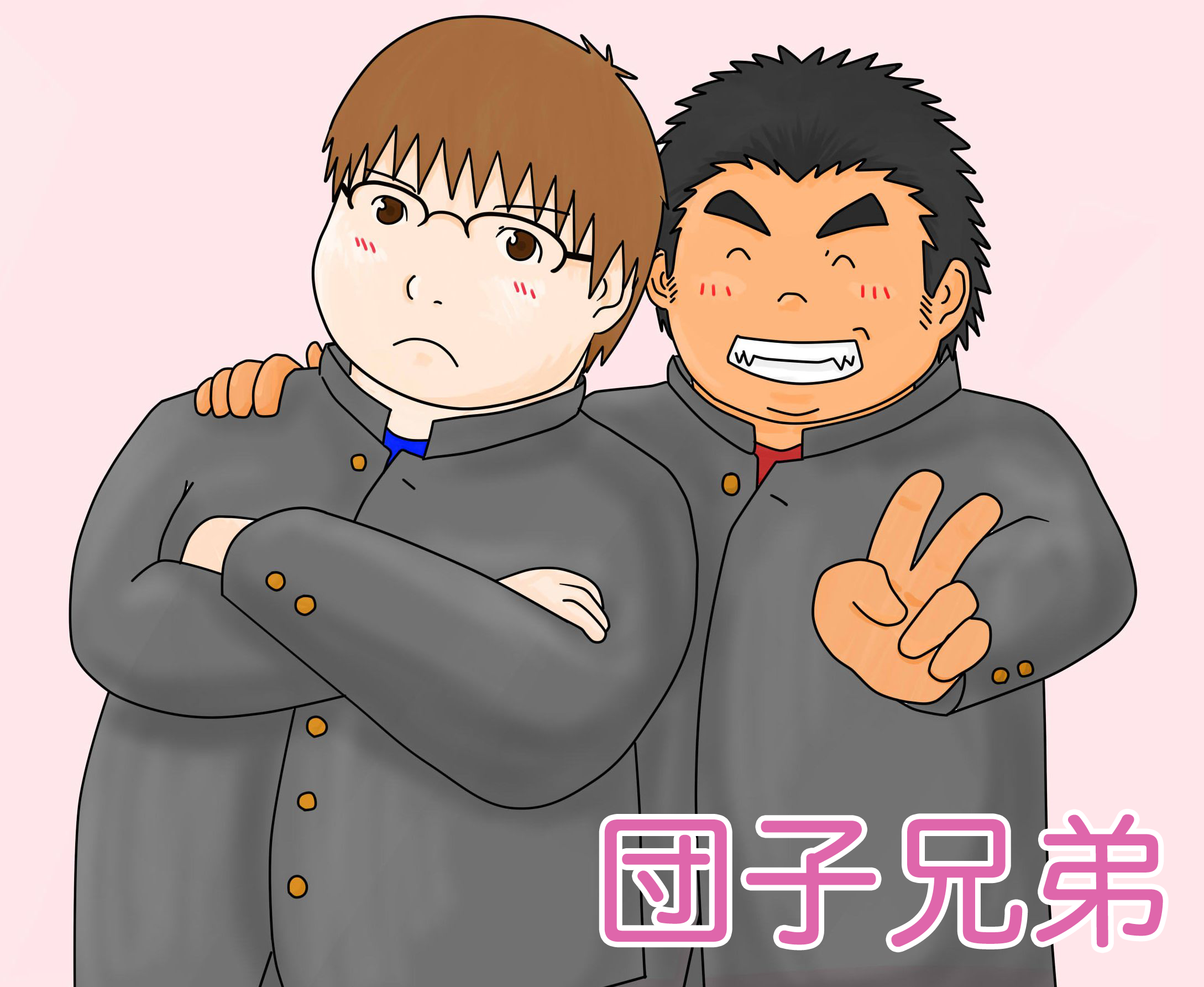牛の聲②
皆さんもうとっくにお察し付いているかと思いますが、話はまだ終わりではありません。
思えば僕らの学級自体、珍しくおとなしいタイプの生徒が集まっていたんですよね。
だからその分やんちゃな牛島くんが特に目立ってしまったことはあったので、そこは少しだけ同情の余地はあるかもしれません。
あの後、濱地くんのいなくなった僕らのクラスルームはまたしても牛島くんの支配下に陥ったわけですから(今思い出すと支配という程のことでもないんですけど)、牛島くんはその後の行動も相変わらずで、ターゲットを決めたらほとんど泣かせるまで嫌がらせを続け、飽きると他の子をまた探すというやり方を繰り返していました。
やがて僕らは5年生に進級し、クラス替えも行われたせいもあってクラスの雰囲気は少し変わっていきました。僕は磯部くんたちと同じクラスになり、そして不幸にも牛島くんと同じクラスになりました。
そして例の問題児。牛島くんはと言うと、その見た目にここ数ヶ月で急激に変化が加わり、日が経過するうちにいじめっ子の風格が露骨に現れたというか...今まで以上に何ともふとましく、あんこ型のルックスにできあがっておりました。
そうなんです、元々ぽっちゃりだった牛島くんは、聞いた話によると半年足らずでジュッキロ以上も増量したんです。その変化は普段から見ていた僕らにも分かるくらいの劇的な変化でした。
思えば僕らの学級自体、珍しくおとなしいタイプの生徒が集まっていたんですよね。
だからその分やんちゃな牛島くんが特に目立ってしまったことはあったので、そこは少しだけ同情の余地はあるかもしれません。
あの後、濱地くんのいなくなった僕らのクラスルームはまたしても牛島くんの支配下に陥ったわけですから(今思い出すと支配という程のことでもないんですけど)、牛島くんはその後の行動も相変わらずで、ターゲットを決めたらほとんど泣かせるまで嫌がらせを続け、飽きると他の子をまた探すというやり方を繰り返していました。
やがて僕らは5年生に進級し、クラス替えも行われたせいもあってクラスの雰囲気は少し変わっていきました。僕は磯部くんたちと同じクラスになり、そして不幸にも牛島くんと同じクラスになりました。
そして例の問題児。牛島くんはと言うと、その見た目にここ数ヶ月で急激に変化が加わり、日が経過するうちにいじめっ子の風格が露骨に現れたというか...今まで以上に何ともふとましく、あんこ型のルックスにできあがっておりました。
そうなんです、元々ぽっちゃりだった牛島くんは、聞いた話によると半年足らずでジュッキロ以上も増量したんです。その変化は普段から見ていた僕らにも分かるくらいの劇的な変化でした。
牛の聲
昔話をします。
僕の小学校ではその昔、牛島くんと言う名のぽっちゃりとした少年がクラスを仕切っていました。
本人曰く自称痩せ型だそうです、実際は普通より、少し肉のついた子供らしい体型だったと思います。
牛島くんはちょっとしたガキ大将タイプの子で、愛嬌のある顔とは裏腹に、命令口調で物を言ったりと、あまり評判は良くありませんでした。学年に一人、二人いそうな子です。
僕は小学校から彼と知り合うことになりましたが、幼い頃から僕は牛島くんが怖くて仕方がありませんでした。
だから、僕や他の同級生のみんなも彼の言うことは何でも聞いていて、ほとんど言いなり状態だったんです。
そんな牛島くんの行動は学年が上がるごとにエスカレートしていって、毎回弱そうな子をイジメのターゲットに選ぶと、とことん追い込むってスタンスでした。ペンをへし折るとか、シューズをゴミ箱の中に突っ込む...。
細いガリガリのひ弱そうな僕みたいなタイプの子は真っ先に選ばれるんです。椅子の下に画鋲をばら撒くとか...当然のようにやってくるんです。
僕もトイレの個室に閉じ込められてホースで水責め?みたいなことをされた時は全身びしょ濡れになってわあわあと泣いてしまって周りから冷やかされたり、もしくは同情された目で見られたりなんて...酷い目に遭いましたよもう。
牛島くんのケライと言うものになればそこまで酷い目に合わないからと言う理由で、彼についてく子達は中にはいたみたいですが、牛島くんは退屈になると仲間内からターゲットを選出して嫌がらせをしていたみたいで...ほんとにどうしようもないって言葉が正しいくらいの子だったんです。
僕の小学校ではその昔、牛島くんと言う名のぽっちゃりとした少年がクラスを仕切っていました。
本人曰く自称痩せ型だそうです、実際は普通より、少し肉のついた子供らしい体型だったと思います。
牛島くんはちょっとしたガキ大将タイプの子で、愛嬌のある顔とは裏腹に、命令口調で物を言ったりと、あまり評判は良くありませんでした。学年に一人、二人いそうな子です。
僕は小学校から彼と知り合うことになりましたが、幼い頃から僕は牛島くんが怖くて仕方がありませんでした。
だから、僕や他の同級生のみんなも彼の言うことは何でも聞いていて、ほとんど言いなり状態だったんです。
そんな牛島くんの行動は学年が上がるごとにエスカレートしていって、毎回弱そうな子をイジメのターゲットに選ぶと、とことん追い込むってスタンスでした。ペンをへし折るとか、シューズをゴミ箱の中に突っ込む...。
細いガリガリのひ弱そうな僕みたいなタイプの子は真っ先に選ばれるんです。椅子の下に画鋲をばら撒くとか...当然のようにやってくるんです。
僕もトイレの個室に閉じ込められてホースで水責め?みたいなことをされた時は全身びしょ濡れになってわあわあと泣いてしまって周りから冷やかされたり、もしくは同情された目で見られたりなんて...酷い目に遭いましたよもう。
牛島くんのケライと言うものになればそこまで酷い目に合わないからと言う理由で、彼についてく子達は中にはいたみたいですが、牛島くんは退屈になると仲間内からターゲットを選出して嫌がらせをしていたみたいで...ほんとにどうしようもないって言葉が正しいくらいの子だったんです。
温水プール②
「次の客待ってような~。おデブの勃起くん」
彼らは外でお客さんを待ちながらぼくに向かって笑った。
少しすると、今度は三人くらいの子どもが入ってきた。
一人は幼稚園くらいでまだ幼い。もう一人は小学生中学年、最後が高学年と、兄弟のように見える。
「しめた!」と一人が笑って彼らを呼びに行く。
そして三人を連れてくると、「いいもん見せてやる」と微笑んだ。
小学生らは年上におびえながらもコクンと頷いた。ぼくはゴクッと唾を飲み込む。
「ほら、出てこいよ。ミニチン」
一人がそう言って、ぼくをプールから上げる。丸裸のぼくに、小学生たちは目を丸くして始めは何も言えないようだった。
「うわぁ」
とだけ声を上げる。幸運にもぼくのあそこはたっていなかったが、それが小さいとからかわれることになる。
「ちいさっ」と遠慮なく中学年の子は笑う。
「もっと笑ってやれ」と、いじめっ子。
「パンツは?」
小学生の高学年の子が尋ねてきた。
「…忘れた」正直に言うと全員が爆笑した。
「マジで!?」
「なしで入るか?普通」
「幼稚園児みてーだな」
口々に言われまたぼくは赤らむ。
小学生の前でプランと何か股から垂らした状態でいるのだ。情けなくて仕様がない。
「うちの弟でも履いてるよ」
兄が幼稚園児の弟を指差す。クスクス笑いながらぼくのアソコを指差している。
「ぼく赤ちゃんじゃないもん」
「きゃはは。そうだよなぁ」
「じゃあ、こいつ赤ちゃん以下?」
「えー俺こんなでぶい赤ん坊いらねー」
お腹と胸を摘んだりもんだりしてきて、笑われる。
「じゃあ、ぼくのパンツあげるよ」
幼稚園児がぼくが嫌がってるのを素直に感じたのだろうか、自らパンツを脱ぎ出した。
全員があっけにとられていると、少年も全裸になりぼくに小さなパンツを渡す。
「はい」
「う…あ…ありが…と…」
その光景はなんとも奇怪な物だったろう。今まで見た事のないシーンに全員が手を叩いてはしゃいだ。
「恥ずかしい!幼稚園児にパンツもらうなよ」
「この子優しい!」
「ってか。見ろよみんな。ちょっときみー立ってみて。このお兄ちゃんの隣」
いじめっ子がぼくの隣にフリチンの園児を立たす。
ぼくはもちろん素っ裸で少年から借りた水着だけ手に持ってる。彼もノーパン状態だ。
そして二つ並ぶ小さい物が…。
彼らは外でお客さんを待ちながらぼくに向かって笑った。
少しすると、今度は三人くらいの子どもが入ってきた。
一人は幼稚園くらいでまだ幼い。もう一人は小学生中学年、最後が高学年と、兄弟のように見える。
「しめた!」と一人が笑って彼らを呼びに行く。
そして三人を連れてくると、「いいもん見せてやる」と微笑んだ。
小学生らは年上におびえながらもコクンと頷いた。ぼくはゴクッと唾を飲み込む。
「ほら、出てこいよ。ミニチン」
一人がそう言って、ぼくをプールから上げる。丸裸のぼくに、小学生たちは目を丸くして始めは何も言えないようだった。
「うわぁ」
とだけ声を上げる。幸運にもぼくのあそこはたっていなかったが、それが小さいとからかわれることになる。
「ちいさっ」と遠慮なく中学年の子は笑う。
「もっと笑ってやれ」と、いじめっ子。
「パンツは?」
小学生の高学年の子が尋ねてきた。
「…忘れた」正直に言うと全員が爆笑した。
「マジで!?」
「なしで入るか?普通」
「幼稚園児みてーだな」
口々に言われまたぼくは赤らむ。
小学生の前でプランと何か股から垂らした状態でいるのだ。情けなくて仕様がない。
「うちの弟でも履いてるよ」
兄が幼稚園児の弟を指差す。クスクス笑いながらぼくのアソコを指差している。
「ぼく赤ちゃんじゃないもん」
「きゃはは。そうだよなぁ」
「じゃあ、こいつ赤ちゃん以下?」
「えー俺こんなでぶい赤ん坊いらねー」
お腹と胸を摘んだりもんだりしてきて、笑われる。
「じゃあ、ぼくのパンツあげるよ」
幼稚園児がぼくが嫌がってるのを素直に感じたのだろうか、自らパンツを脱ぎ出した。
全員があっけにとられていると、少年も全裸になりぼくに小さなパンツを渡す。
「はい」
「う…あ…ありが…と…」
その光景はなんとも奇怪な物だったろう。今まで見た事のないシーンに全員が手を叩いてはしゃいだ。
「恥ずかしい!幼稚園児にパンツもらうなよ」
「この子優しい!」
「ってか。見ろよみんな。ちょっときみー立ってみて。このお兄ちゃんの隣」
いじめっ子がぼくの隣にフリチンの園児を立たす。
ぼくはもちろん素っ裸で少年から借りた水着だけ手に持ってる。彼もノーパン状態だ。
そして二つ並ぶ小さい物が…。
一路の夏
小さな頃からぼくは注目されるのが大好きで、いつも人の気を引こうと必死だった
ただ、誰かに構って欲しかっただけだったと思う。実際、性格は内向的で、人見知りは山ほどした。
近所の友達はみんな大人しい子が揃っていて、ぼくは彼らを盛り上げ役を務めていた。夏は川の中に服のまま飛び込んで馬鹿をして彼らを笑わせたりと、やりたい放題の日常を送っていた。
そんなぼくには従兄弟のお兄ちゃんがいて、夏休みになると毎年、お兄さんの家に遊びに行った。お兄ちゃんは大分年が離れているけれど、ぼくのことをすごく可愛がってくれた。
「一路はドラ◯もんみたいで可愛いな〜」
お兄ちゃんはそう言いながらぼくを膝の上に乗せて頭を撫でてくれた。ぼくも甘えるのが大好きだったので、お兄ちゃんの膝の上で調子のいい事をいいながら、お兄ちゃんを笑わせていた。お兄ちゃんの膝の上で寝てしまう事だって何度かあったくらいだ。
そんなお兄ちゃんが笑ってくれるのが大好きだったぼくは、お兄ちゃんが笑ってくれるなら何でもした。テレビのしんちゃんのようにケツだけ星人をやったり、ちんちんにゾウサンを描いて踊ったりもした。大抵パンツを脱ぐとお兄ちゃんは喜んで褒美にお菓子をくれるので、お兄ちゃんの前ではパンツを脱ぐのは当たり前になっていたんだと思う。
暇になるとぼくはいつも裸でおちんちんを突き出してみせた。もちろん、お兄ちゃんのお母さんに見つかると、ぼくのお母さんに報告されて痛い目にあった。
そして、そんなある年の夏の日ことだった。ぼくが小学三年生になる頃のこと。
お兄ちゃんと二人でお兄ちゃんの家でゲームをしていると、珍しくお兄ちゃんの友達が遊びに来た。
「こんにちは」
痩せてメガネをかけたお兄ちゃんは「小石です」と名乗ってぼくの頭を撫でてくれた。
「思ったよりもずっと可愛いじゃん」
小石さんはそう笑ってお兄ちゃんに相づちをうっているのが見えた。可愛いと言いわれるのは大好きだったので悪い気はしなかった。小石さんはカバンからカメラを取り出して、ぼくに見せて来た。
「何か知ってる?」
「カメラでしょ?それくらい知ってるよ」
ぼくは自信満々に答えた。けれど、デジタルカメラは見るのが初めてだった。見てるだけでも夢中になった。
「うん。今日は一路くん撮りに来たんだよ。な、そうだよな」
「ああ」とお兄ちゃん小石さんに相づちをうつ。
「ぼくを?本当?」
嬉しくなってぼくは一人でばたばた飛び回る。そして満面の笑顔でお兄ちゃんと小石さんに尋ねた。
「ねっ。それで、何を撮るの?」
んー。と小石さんはちょっとの間考える振りをしてみせ、そして少しして何かお気に入りのポーズとかある?と、僕に尋ねて来た。
ポーズ?と言われてもなかなかすぐには動けない。カメラを向けられたままモジモジしていると、お兄ちゃんが呑気な口調でぼくに声をかけた。
「一路、いつものやつやれよ」
「いつもの?」
ぼくは眉をひそめる。いつものって?と聞いた。
「しんちゃんのマネ。一路、大好きだからな。振り付け完璧なんだよな」
「そうなのかー。そりゃいい」
小石さんは大げさに驚いた様な声をあげて、歯を見せて笑みを向けた。
「しんちゃんのマネってさ。例えばどんなことだい?」
「ちょっとーお兄ちゃん。お母さんに怒られるよ!」
見つかったらどうなるかは想像するだけで怖かった。もしかしたら夏休みの間外出禁止を食らうかもしれない。けれど、怒ってもお兄ちゃんはヘラヘラと笑ってみるだけだ。
「はは。いいだろ。お母さんには内緒だって。約束するよ」
「やだよ。去年、お兄ちゃんのせーで、お尻打たれたもん!」
「お前も飴なんかでつられるからだろ?」
お互いにらみ合っていると小石さんが手を打って仲へ入って来た。
「な。いいアイディアあるんだけどさ。お前と一路くんが二人とも互いの母ちゃんには言わないって約束すればいいんだろ?」
「ん?ああ。別にこのデブちんが破らなけりゃ問題ないさ」
「ぼくも、兄ちゃんが破らなけりゃ問題ないもん」
意地を張って太い腕を無理矢理組んでいると小石さんはバッグから一枚の紙を取り出した。
何これ。とぼくの問いに、小石さんはいいからいいから。とそこに何かを書き込んでいく。
まだ習った事の無い漢字がそこにずらっと並ぶ。
「一路くん、これ読める?」
ぼくは首を振る。
契約書、とお兄ちゃんが代わりに答えた。何それ。とぼくは首を傾げる。
ただ、誰かに構って欲しかっただけだったと思う。実際、性格は内向的で、人見知りは山ほどした。
近所の友達はみんな大人しい子が揃っていて、ぼくは彼らを盛り上げ役を務めていた。夏は川の中に服のまま飛び込んで馬鹿をして彼らを笑わせたりと、やりたい放題の日常を送っていた。
そんなぼくには従兄弟のお兄ちゃんがいて、夏休みになると毎年、お兄さんの家に遊びに行った。お兄ちゃんは大分年が離れているけれど、ぼくのことをすごく可愛がってくれた。
「一路はドラ◯もんみたいで可愛いな〜」
お兄ちゃんはそう言いながらぼくを膝の上に乗せて頭を撫でてくれた。ぼくも甘えるのが大好きだったので、お兄ちゃんの膝の上で調子のいい事をいいながら、お兄ちゃんを笑わせていた。お兄ちゃんの膝の上で寝てしまう事だって何度かあったくらいだ。
そんなお兄ちゃんが笑ってくれるのが大好きだったぼくは、お兄ちゃんが笑ってくれるなら何でもした。テレビのしんちゃんのようにケツだけ星人をやったり、ちんちんにゾウサンを描いて踊ったりもした。大抵パンツを脱ぐとお兄ちゃんは喜んで褒美にお菓子をくれるので、お兄ちゃんの前ではパンツを脱ぐのは当たり前になっていたんだと思う。
暇になるとぼくはいつも裸でおちんちんを突き出してみせた。もちろん、お兄ちゃんのお母さんに見つかると、ぼくのお母さんに報告されて痛い目にあった。
そして、そんなある年の夏の日ことだった。ぼくが小学三年生になる頃のこと。
お兄ちゃんと二人でお兄ちゃんの家でゲームをしていると、珍しくお兄ちゃんの友達が遊びに来た。
「こんにちは」
痩せてメガネをかけたお兄ちゃんは「小石です」と名乗ってぼくの頭を撫でてくれた。
「思ったよりもずっと可愛いじゃん」
小石さんはそう笑ってお兄ちゃんに相づちをうっているのが見えた。可愛いと言いわれるのは大好きだったので悪い気はしなかった。小石さんはカバンからカメラを取り出して、ぼくに見せて来た。
「何か知ってる?」
「カメラでしょ?それくらい知ってるよ」
ぼくは自信満々に答えた。けれど、デジタルカメラは見るのが初めてだった。見てるだけでも夢中になった。
「うん。今日は一路くん撮りに来たんだよ。な、そうだよな」
「ああ」とお兄ちゃん小石さんに相づちをうつ。
「ぼくを?本当?」
嬉しくなってぼくは一人でばたばた飛び回る。そして満面の笑顔でお兄ちゃんと小石さんに尋ねた。
「ねっ。それで、何を撮るの?」
んー。と小石さんはちょっとの間考える振りをしてみせ、そして少しして何かお気に入りのポーズとかある?と、僕に尋ねて来た。
ポーズ?と言われてもなかなかすぐには動けない。カメラを向けられたままモジモジしていると、お兄ちゃんが呑気な口調でぼくに声をかけた。
「一路、いつものやつやれよ」
「いつもの?」
ぼくは眉をひそめる。いつものって?と聞いた。
「しんちゃんのマネ。一路、大好きだからな。振り付け完璧なんだよな」
「そうなのかー。そりゃいい」
小石さんは大げさに驚いた様な声をあげて、歯を見せて笑みを向けた。
「しんちゃんのマネってさ。例えばどんなことだい?」
「ちょっとーお兄ちゃん。お母さんに怒られるよ!」
見つかったらどうなるかは想像するだけで怖かった。もしかしたら夏休みの間外出禁止を食らうかもしれない。けれど、怒ってもお兄ちゃんはヘラヘラと笑ってみるだけだ。
「はは。いいだろ。お母さんには内緒だって。約束するよ」
「やだよ。去年、お兄ちゃんのせーで、お尻打たれたもん!」
「お前も飴なんかでつられるからだろ?」
お互いにらみ合っていると小石さんが手を打って仲へ入って来た。
「な。いいアイディアあるんだけどさ。お前と一路くんが二人とも互いの母ちゃんには言わないって約束すればいいんだろ?」
「ん?ああ。別にこのデブちんが破らなけりゃ問題ないさ」
「ぼくも、兄ちゃんが破らなけりゃ問題ないもん」
意地を張って太い腕を無理矢理組んでいると小石さんはバッグから一枚の紙を取り出した。
何これ。とぼくの問いに、小石さんはいいからいいから。とそこに何かを書き込んでいく。
まだ習った事の無い漢字がそこにずらっと並ぶ。
「一路くん、これ読める?」
ぼくは首を振る。
契約書、とお兄ちゃんが代わりに答えた。何それ。とぼくは首を傾げる。
温水プール
ぼくは家から少し離れた温水プールに家族と来ていた。
お兄ちゃんとお姉ちゃんとぼくとお母さん。珍しくお兄ちゃんの提案だ。
「ほら、いくよ」
車を降りてお母さんがぼくを呼ぶ。広々とした館内はエアコンが効いてて涼しい。
「4人で」
大学生のお兄ちゃんチケットを買って、ぼくはお母さんとお姉ちゃんと別れて更衣室に進むことに。
しかし、そこで問題発生。
「あーーー!!!!」
プールの用意をまさぐって悲鳴をあげるぼく。
なんと水泳バッグの中に入れたと思ったはずのパンツが入っていないのだ。
「そんなぁ」
ぼくはお兄ちゃんを見る。とっくに状況を理解しているお兄ちゃんもあきれた表情でぼくの泣きそうな顔を見つめる。
「お前は・・・本当にぼーっとしてんな。どうすんだ?」
「取りに行く」
「馬鹿。往復で1時間もかかるんだぞ」
「売ってないの?」
「高いだろ。こういうところで買う水着は。プール代、誰が出したと思ってるんだよ?」
ケチ、と呟いた。
「お前が忘れるから悪いんだろ」
お兄ちゃんはぼくのまん丸のお尻を平手で叩く。
ぴしゃりといい音がする。慌ててぼくは前とお尻をタオルで隠した。
「やめてよ」
「しゃーねーな。そのまま泳げ。さっき、見たけど今日誰もいなかったから大丈夫だ」
「や、やだよ!子どもじゃないし」
「子どもだろ」
「恥ずかしいじゃん」
「ばーか。そんなまん丸の体型してるから恥ずかしいんだよ。普段から言ってるだろ?痩せろってさ」
お兄ちゃんが今度はぼくのお腹をつかもうとする。
とっさにタオルが落ちて、お兄ちゃんは楽しそうに笑った。
「恥ずかしがることないって。お前まだ、小学生だろ?」
「中学生だよ!」
今年で中学生になったばかりのぼくは必死になって言い返す。
「ん?そうだっけ?」
「なんで忘れるのさ」
ぼくは文句を言いながらまたタオルを腰に巻こうとすると、今度はタオルを取り上げられた。
「ここはまだ小学生だろ?」
まだ毛の生えていないつるつるのぼくの股間を指さしてお兄ちゃんはそう言った。
「もおおおー!返してよー」
「ばーか。タオル巻きながらどうやって泳ぐんだよ」
結局お兄ちゃんはタオルごとさっさとロッカーにしまって鍵をかけてしまった。
フリチンのままぼくは途方に暮れる。
「ほら、何やってんだ。早く行くぞ」
それでも、お兄ちゃんは全く気にしていないようで、全裸のぼくを引っ張ってプールへと連れて行った。
「さいてーー」
お姉ちゃんはプールでフリチンのぼくを冷ややかな目で見つめた。
「買ってあげなさいよ。パンツくらい」
お母さんも帽子を被って下半身裸のぼくを哀れんだ様子で見つめた。
「やだよ。こいつのサイズのパンツたけーんだぜ?二千円!」
「そうなの?」
値段を言われ、お母さんは「なら仕方ないわ」とプールにさっさと入っていった。
「ほら、行くぞ。ちんちん」
「ちんちんって言わないでよ!」
ぼくは顔を赤くしてお兄ちゃんを追いかけた。
最初は恥ずかしがっていたぼくだが、案外プールの中に入ってしまえば気にならなかった。
いろんなプールがあり、ぼくは出る時はダッシュして他のプールに飛び込む。
お兄ちゃんととお母さんがその度に大笑いする。真面目なお姉ちゃんは相変わらず、冷たい目でぼくを見つめている。
そして、それから家族で数時間泳ぎ、昼過ぎになった。
お姉ちゃんはが「お腹すいた」とお母さんに告げて、みんなでお昼を食べに行くことになる。
「えーー。まだお腹すいてないよ。それにまだ全然泳いでないし!」
まだ泳ぎ足らないぼくは一人でぶつぶつ文句を言う。
「もう、二時間も泳いだじゃない」お姉ちゃんが悲鳴に近いくらいの大声でぼくを避難する。
「もう、無理よ、私は。お腹すいたんだから。一分も泳がない」
「お姉ちゃん、太るよ」
ぼくがからかうと血相を変えて追いかけられた。ぼくはプールへと飛び込む。
「じゃあ、あたしらだけで食べにいきましょ。またあの子ここに迎えにこればいいし」
「迎えに来なくてもいいわよ。あのデブなんて」と、お姉ちゃんはまだ怒っている。
お兄ちゃんはぼくにロッカーの鍵だけを渡すと、そのまま行ってしまった。
数分後、お兄ちゃんパンツだけでも借りればよかったと後悔したが遅かった。
お兄ちゃんとお姉ちゃんとぼくとお母さん。珍しくお兄ちゃんの提案だ。
「ほら、いくよ」
車を降りてお母さんがぼくを呼ぶ。広々とした館内はエアコンが効いてて涼しい。
「4人で」
大学生のお兄ちゃんチケットを買って、ぼくはお母さんとお姉ちゃんと別れて更衣室に進むことに。
しかし、そこで問題発生。
「あーーー!!!!」
プールの用意をまさぐって悲鳴をあげるぼく。
なんと水泳バッグの中に入れたと思ったはずのパンツが入っていないのだ。
「そんなぁ」
ぼくはお兄ちゃんを見る。とっくに状況を理解しているお兄ちゃんもあきれた表情でぼくの泣きそうな顔を見つめる。
「お前は・・・本当にぼーっとしてんな。どうすんだ?」
「取りに行く」
「馬鹿。往復で1時間もかかるんだぞ」
「売ってないの?」
「高いだろ。こういうところで買う水着は。プール代、誰が出したと思ってるんだよ?」
ケチ、と呟いた。
「お前が忘れるから悪いんだろ」
お兄ちゃんはぼくのまん丸のお尻を平手で叩く。
ぴしゃりといい音がする。慌ててぼくは前とお尻をタオルで隠した。
「やめてよ」
「しゃーねーな。そのまま泳げ。さっき、見たけど今日誰もいなかったから大丈夫だ」
「や、やだよ!子どもじゃないし」
「子どもだろ」
「恥ずかしいじゃん」
「ばーか。そんなまん丸の体型してるから恥ずかしいんだよ。普段から言ってるだろ?痩せろってさ」
お兄ちゃんが今度はぼくのお腹をつかもうとする。
とっさにタオルが落ちて、お兄ちゃんは楽しそうに笑った。
「恥ずかしがることないって。お前まだ、小学生だろ?」
「中学生だよ!」
今年で中学生になったばかりのぼくは必死になって言い返す。
「ん?そうだっけ?」
「なんで忘れるのさ」
ぼくは文句を言いながらまたタオルを腰に巻こうとすると、今度はタオルを取り上げられた。
「ここはまだ小学生だろ?」
まだ毛の生えていないつるつるのぼくの股間を指さしてお兄ちゃんはそう言った。
「もおおおー!返してよー」
「ばーか。タオル巻きながらどうやって泳ぐんだよ」
結局お兄ちゃんはタオルごとさっさとロッカーにしまって鍵をかけてしまった。
フリチンのままぼくは途方に暮れる。
「ほら、何やってんだ。早く行くぞ」
それでも、お兄ちゃんは全く気にしていないようで、全裸のぼくを引っ張ってプールへと連れて行った。
「さいてーー」
お姉ちゃんはプールでフリチンのぼくを冷ややかな目で見つめた。
「買ってあげなさいよ。パンツくらい」
お母さんも帽子を被って下半身裸のぼくを哀れんだ様子で見つめた。
「やだよ。こいつのサイズのパンツたけーんだぜ?二千円!」
「そうなの?」
値段を言われ、お母さんは「なら仕方ないわ」とプールにさっさと入っていった。
「ほら、行くぞ。ちんちん」
「ちんちんって言わないでよ!」
ぼくは顔を赤くしてお兄ちゃんを追いかけた。
最初は恥ずかしがっていたぼくだが、案外プールの中に入ってしまえば気にならなかった。
いろんなプールがあり、ぼくは出る時はダッシュして他のプールに飛び込む。
お兄ちゃんととお母さんがその度に大笑いする。真面目なお姉ちゃんは相変わらず、冷たい目でぼくを見つめている。
そして、それから家族で数時間泳ぎ、昼過ぎになった。
お姉ちゃんはが「お腹すいた」とお母さんに告げて、みんなでお昼を食べに行くことになる。
「えーー。まだお腹すいてないよ。それにまだ全然泳いでないし!」
まだ泳ぎ足らないぼくは一人でぶつぶつ文句を言う。
「もう、二時間も泳いだじゃない」お姉ちゃんが悲鳴に近いくらいの大声でぼくを避難する。
「もう、無理よ、私は。お腹すいたんだから。一分も泳がない」
「お姉ちゃん、太るよ」
ぼくがからかうと血相を変えて追いかけられた。ぼくはプールへと飛び込む。
「じゃあ、あたしらだけで食べにいきましょ。またあの子ここに迎えにこればいいし」
「迎えに来なくてもいいわよ。あのデブなんて」と、お姉ちゃんはまだ怒っている。
お兄ちゃんはぼくにロッカーの鍵だけを渡すと、そのまま行ってしまった。
数分後、お兄ちゃんパンツだけでも借りればよかったと後悔したが遅かった。